スマホでサンマが焼ける日ーコラムー第5回 花を贈るように電気を送る
| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |
一般社団法人エネルギー情報センター
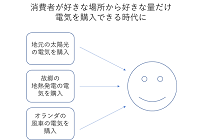
電気のデジタル化によって、電力の世界にも近い将来「電気をシェア(共有)」する時代、「エネルギーシェアの時代」がやってくるのではないかと考えています。
執筆者:一般社団法人エネルギー情報センター
理事 江田健二
富山県砺波市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)に入社。エネルギー/化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカ等のプロジェクトに参画。その後、RAUL株式会社を起業。主に環境・エネルギー分野のビジネス推進や企業の社会貢献活動支援を実施。一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人CSRコミュニケーション協会理事、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員等を歴任。
記事出典:書籍『スマホでサンマが焼ける日 電気とエネルギーをシェアする未来の「新発想論」』(2017年)
コーヒー代と電気料金を一緒にお会計
世の中のものがデジタル化することによって起こる大きなメリットが「シェアできるようになる」ことだと話しました。実は電気のデジタル化によって、電力の世界にも同じようなことが起こると私は考えています。すなわち、近い将来「電気をシェア(共有)」する時代、「エネルギーシェアの時代」がやってくるのでは、ということです。
今まで電気利用というのは、ある家庭に送られている電気を使えるのはその家に住んでいる人だけ、ある会社、あるお店に送られている電気を使えるのはその会社の人、そのお店で働いている人だけでした。つまり電気は特定の場所にいる人の「占有物」であったわけです。しかしこれからは、たとえばあるカフェにいるお客さんなら誰でもそのカフェが提供する電気を使える、すなわち電気エネルギーを「占有・独占から共有」する時代になると思います。
「もうすでに、電源がついていて自由に電気を使えるカフェがあるじゃないか」という方もいるでしょう。確かに最近そういったカフェが増えていて、コワーキングスペース(共有オフィス)のようにカフェにパソコンを持ちこんで仕事をしている人も目立ちます。お客さんから電気使用料をとっているお店はありませんが、その理由として、誰がどれだけの電気を使ったかが分からない、ということがあると思います。
しかし近い将来、お店側がスマートメーターや各種機器を設置すれば、お客さんごと、端末ごとの電気使用量がデータ化されて分かるようになるでしょう。各端末のIDが認識されて、今この端末にこれだけ充電した、ということが簡単に認識されるので、個別に電気使用量を課金できるようになるのです。たとえばお会計の際に「コーヒーと電気料金を合計して、○○円になります!」といったようになるかもしれません。こうなればお客さん側も、何時間もお店の電気を使ってしまっている、といった気兼ねも必要なくなりますし、お店側にとっても非常に有り難い話です。
こうしたことが可能になれば、そこから、いろいろなお店で「電気の販売」のような今までにはなかった新しいビジネスが生まれるはずです。このように、スマートメーターがきっかけとなり様々なことが可能になる。この、端末ごとの電気使用データが取れるということが、消費者の生活にとってとても重要なことなのです。そして、それがこの後お話しする「ワイヤレス給電」や「分散型発電」の話に広がっていきます。
花を贈るように電気を送る
2016年4月の電力自由化後、自分が住んでいる場所から遠く離れた電力会社、発電所の電気も買うことができるようになりました。ですがまだ、自宅から遠く離れた場所にある電力会社から電気を買う人はごくわずかです。多くの人がもっと自由に好きな電力会社から同じ料金で電気を買えるようにするためにも、電気のデジタル化(データ化)と、電気のデータを柔軟に取り引きできるシステムの構築が必要になってきます。
分かりやすい例で説明すると、お金の流れです。たとえばある人が北海道で入金した1万円を別の人が沖縄で引き出す場合、当たり前ですがその1万円札は入金した人の財布から出したお札ではなく、銀行のシステムが数字上、データ上で北海道から沖縄へ1万円が送られたことにしているわけです。それと同じように、将来北海道の風車で作った電気を沖縄の人が使いたいと思ったとき、実際の電気の流れと電気取り引きの数値的な流れを別々にすれば、もっと自由な電気の取り引きが可能になるのです。
これは、全国どこへでも花を贈ることができるサービス「花キューピット」(インターネット 花キューピット)も同じような発想です。東京にいる息子が九州の実家のお母さんにカーネーションをプレゼントするとき、そのカーネーションは東京の花屋さんから九州に送られるわけではなく、お母さんの家の近くの花屋さんや卸売り市場から送られるのです。
このように電気をデータとして商取り引きできるようになれば、たとえばアフリカの発電所で作られた電気を日本から簡単に買うこともできるようになるわけです。将来的にはこのように、電気の「実際の流れ」と「電気の利用の流れ(履歴)」は今以上に分かれていくのではないかと思います。そうなって世界中で自由に電気のやりとりができるようになれば、非常にいろいろなメリットが考えられます。
この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。
無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです
執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター
EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。
| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |
| 電話番号 | 03-6411-0859 |
| 会社HP | http://eic-jp.org/ |
| サービス・メディア等 | https://www.facebook.com/eicjp
https://twitter.com/EICNET |
関連する記事はこちら
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年03月26日
系統用蓄電池のアグリゲーションについて|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ
2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、デジタルグリッド株式会社の豊田祐介氏が講演した「系統用蓄電池のアグリゲーション」について、その要約をご紹介します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年03月18日
系統用蓄電池での安全面や各種補助金について|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ
2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、電気予報士の伊藤 菜々 氏が講演した「系統用蓄電池での安全面や各種補助金」について、その要約をご紹介します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年03月18日
系統用蓄電池の導入事例について|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ
2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、株式会社パワーエックスの小嶋 祐輔 氏が講演した「系統用蓄電池の導入事例」について、その要約をご紹介します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年03月18日
系統用蓄電池ビジネスの最前線|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ
2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、株式会社AnPrenergyの村谷 敬 氏が講演した「系統用蓄電池ビジネスの最前線」について、その要約をご紹介します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2024年03月12日
EVと並んで蓄電池と大きな関わりのある「エネルギーマネジメント」にテーマを絞って、蓄電池の今と未来を全6回に渡ってご紹介していきます。
















































