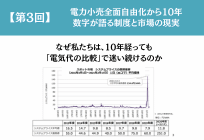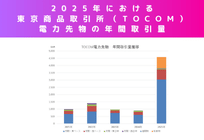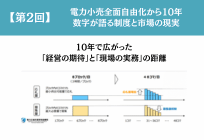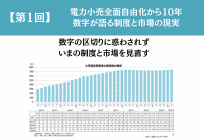【第2回】再選トランプ政権の関税政策とエネルギー分野への波紋 〜日本企業・自治体の現場対応から読み解く実務課題と展望〜
| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |
一般社団法人エネルギー情報センター

2025年4月に本格発動されたトランプ政権の「相互関税」政策は、日本のエネルギー分野にも広範な影響をあたえています。前回の第1回では、制度の背景や構造的リスク、太陽光・LNG・蓄電池といった主要分野への影響の全体像を整理しました。 本稿ではその続編として、実際に通商環境の変化を受けた企業・自治体の現場対応に焦点をあて、最新の実務動向と政策支援の現状を整理します。

出典:The official photostream of the White House
企業の対応:関税政策に対応した調達・生産戦略の再編
トランプ政権による相互関税政策の本格発動は、日本企業のエネルギー関連ビジネスにも幅広い影響を及ぼしています。とくにLNG(液化天然ガス)、再生可能エネルギー機器、蓄電池、電力インフラ部材など、さまざまな分野で通商リスクやコスト上昇への備えが急務となっています。
企業各社は、調達先の分散や現地生産の強化、制度の活用を組み合わせながら、安定した事業運営に向けた対応を進めています。ここでは、それぞれの分野での具体的な取り組みを整理します。
(1) LNG調達の多元化と契約戦略
トランプ政権による相互関税政策は、LNG分野でも米国依存のリスクをあらためて浮き彫りにしています。鉄鋼・アルミ関税の影響による米国LNG輸出基地の建設コスト上昇や遅延が進むなか、日本企業は調達先の分散を急ピッチで進めつつあります。
2025年4月の日本のLNG輸入実績では、アメリカからの輸入量が191千トンとなり、前年同月比で56.3%減少しました(財務省貿易統計 2025年5月速報より)。前年2024年4月実績(437千トン、前年同月比+ 38.6%)と比較しても、短期間での大幅な減少が確認され、減速傾向が一層鮮明になっています。
JERA(日本最大級の電力・エネルギー企業)は2025年5月、米NextDecade社と年間200万トン・20年契約を新たに締結。米国枠を一定確保しつつ、中東・豪州・カナダとの分散契約を拡充しています。特にカタールとの年間300万トン契約(3月締結)が中核となり、通商リスクを抑えたポートフォリオが構築されつつあります。
三菱商事はカナダ西岸の「LNGカナダプロジェクト」に15%出資しており、2025年夏以降の稼働を控えます。年間1,400万トン規模の生産に加え、今後は生産能力の倍増も視野に入れ、安定供給源の確保を進めています。

出典:財務省『令和 6年 4月分貿易統計(確々報)、令和 7年 4月分貿易統計(確報)』をもとに筆者作成。
(2) 蓄電池・電気部材の生産移管
2025年5月時点で、対中関税の強化は再エネ関連部材のサプライチェーン全体に波及しています。特に電池や電気部材では中国依存のリスク回避が課題となり、各社が生産体制の再編を加速させています。
日立ハイテクはポーランド新工場の稼働を開始し、EU原産地ルールの活用によって対米輸出ルートを再構成。関税負担を回避しつつ、供給の安定性も高めています。
一方、パナソニックは「Chinaプラスワン」戦略の一環として、豪州・ASEAN・北米で素材調達や生産拠点の拡大を進行中です。あわせて、米国インフレ抑制法(IRA)の税制優遇措置も活用し、北米域内の電池工場建設や生産能力の拡充に取り組んでいます。
これらの動きは、関税対策にとどまらず、地政学リスクの分散や市場競争力の確保といった複合戦略として展開されています。今後も政策変更や供給構造の変化を踏まえた柔軟な体制整備が重要な経営課題となるでしょう。
(3) インフラ用鋼材・部材コストの上昇と国内供給網の強化
鉄鋼・アルミニウム関税の継続強化は、電力・エネルギーインフラの各種部材コストを押し上げています。送電鉄塔、太陽光架台、風力タワー、変圧器鉄心などの構造用鋼材やアルミ部材の価格上昇が顕在化し、事業コストにも波及しています。
このため、国内調達体制の再構築が進展しています。JFEスチールなどの鉄鋼メーカーは高強度鋼材や特殊鋼板の国内生産体制を強化し、部材メーカーとも連携を深めています。
また、送配電設備を支える電力系統部材でも同様の動きが進んでいます。住友電工や古河電工は、変圧器用電磁鋼板や高電圧ケーブル分野での国内設備投資を拡大し、エネルギーインフラ整備を下支えしています。こうした対応は通商リスクを見据えた分散戦略の一環として位置付けられます。
2. 自治体の対応:関税政策によるエネルギー調達リスクへの現場対応
トランプ政権による相互関税政策は、自治体が進める再生可能エネルギー導入やインフラ整備にも一定の影響を及ぼしています。
特に部材価格の上昇や納期の不安定化を受け、現場では安定調達に向けた独自の対応が本格化しています。こうした取り組みは、地域のエネルギー自立や災害時のレジリエンス向上にもつながっています。
(1) 国産再エネ機器への調達切替
関税強化の影響により、海外製太陽光パネルや蓄電池の価格上昇・納期遅延が顕在化しています。これを受け、自治体では調達方針の見直しが進み、国産機器の優先採用へと転換する動きが広がりつつあります。
北九州市では、小中学校など公共施設の太陽光発電設備更新において国産パネルの導入を拡大。加えて、老朽設備のリユース活用によるコスト抑制と循環型経済(サーキュラーエコノミー)推進も同時に進められています。こうした取り組みは、海外サプライチェーンの不安定化に備えた地域独自の安定供給策の一例となっています。
他の自治体でも、エネルギー関連機器の調達における国産品への切り替えや調達先の多様化が進んでいます。たとえば、ある自治体では海外製蓄電池の価格上昇を受け、国内メーカーとの連携強化を通じた安定供給体制の構築が図られています。
3. 制度支援と実務課題:政府の関税対策パッケージ
トランプ政権の相互関税政策を受け、日本政府も企業や自治体の現場対応を支える制度支援を多面的に展開しています。
価格高騰対策、中小企業支援、資源調達リスク軽減といった政策パッケージが整備され、柔軟な実務対応を後押ししています。ここでは主要な支援策と課題対応の現状を整理します。
(1) 緊急経済対策による価格高騰抑制
2025年4月の関税措置発動を受け、日本政府は速やかに緊急経済対策パッケージを編成し、燃料・電力価格の高騰リスクに対応しました。5月には追加の経済対策も決定され、家庭や事業者のエネルギー負担軽減策が本格的に実施されています。
この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。
無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです
執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター
EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。
| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |
|---|---|
| 所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |
| 電話番号 | 03-6411-0859 |
| 会社HP | http://eic-jp.org/ |
| サービス・メディア等 |
https://www.facebook.com/eicjp
https://twitter.com/EICNET |
関連する記事はこちら
一般社団法人エネルギー情報センター
2026年02月11日
電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第3回】なぜ私たちは、10年経っても「電気代の比較」で迷い続けるのか
電力小売全面自由化から10年が経過し、電気料金のメニューや契約形態は大きく多様化しました。 一方で、どの電気契約が有利なのかという問いは、いまも多くの現場で解消されないまま残っています。 見積書を並べ、単価を比較し、条件を読み込んでも、最後の判断に踏み切れない。こうした迷いは、単なる理解不足や情報不足として片づけにくいものになっています。 判断が難しくなる背景には、情報の量ではなく、比較に持ち込まれる情報の性質が揃わなくなったことがあります。 単価のように「点」で示せる情報と、価格変動や運用負荷のように時間軸を含む「線」の情報が、同じ比較枠の中で扱われやすくなっているためです。 本稿では、この混線がどこで起きているのかを整理します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2026年01月19日
2025年の電力先物市場:年間取引量4,583GWhで過去最高更新、年度物導入と中部エリア上場を控えた市場の変化
価格変動リスクへの対応を意識した取引行動が、実務レベルで具体化し始めた一年となりました。 制度面では年度物取引の導入、取引環境では流動性改善やコスト低減策が進み、企業側では中長期のヘッジ設計を見直す動きが重なりました。こうした複数の要因が同時に作用した結果、東京商品取引所(TOCOM)における電力先物の年間取引量は約4,583GWhと、前年比約5倍に拡大し、過去最高を更新しています。 中でも、東エリア・ベースロード電力先物が前年比約5倍、西エリア・ベースロード電力先物が前年比約3倍と伸長し、主要商品の取引が全体を押し上げた形となりました。加えて、2025年5月に取引を開始した年度物取引も、市場拡大を牽引する要素となっています。 本稿では、2025年通年の動向を中心に、市場拡大の背景と今後の論点を整理します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2026年01月19日
電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離
「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年12月31日
電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す
「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年12月27日
政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略
これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。