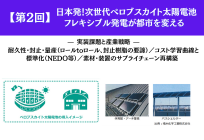FIT制度、2025年度から太陽光・風力・水力の一部が単価変更、再エネ賦課金は3.98円で前年度から14%増加
| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |
一般社団法人エネルギー情報センター

本記事では、2025年度以降のFIT(固定価格買取)制度に関する再エネの動向を見ていきます。太陽光発電は初期投資支援スキームが導入され、また洋上風力は価格調整スキームが導入されるなど、今後新たな形での再エネ事業開発が進められることが期待されます。
日本は現状では国産のエネルギー資源に乏しく、国土を山と深い海に囲まれるなどの地理的制約を抱えており、過去に幾度もエネルギー安定供給の危機に見舞われてきました。1973年の石油危機に際しては、調達国の多角化等を進めることに加え、「ムーンライト計画」などによる省エネ、「サンシャイン計画」による再エネなどの石油代替エネルギー源の開発・活用を進めてきました。
しかし2011年の福島第一原子力発電所事故以降、原子力発電所の多くが停止した結果、化石燃料に対する依存が高まり、その多くを海外からの輸入に頼るという、エネルギー需給構造上の脆弱性が再び顕在化することとなりました。
そこで再エネ拡大の機運が高まり、2011年当時、首相だった菅直人氏は「固定価格買い取り制度(FIT)」の成立後に退陣しました。2012年7月にFIT制度が本格開始し、当時大規模水力ダムを中心に凡そ10%であった電源構成に占める再エネ比率は、自然エネルギー財団の調査によると2023年度には26.1%にまで拡大しました。また最新のエネルギー基本計画を参照すると、世界全体の対比で見ると、日本は山林が多いために陸上の平地面積が小さく、また洋上は急峻な海底地形であるなど、地理的制約がある中で、導入容量は再エネ全体で世界第6位(2022年度)となるなど、導入が着実に進展しています。
FIT開始後も、日本のエネルギー業界ではバランスの取れたエネルギー供給体制の構築を目指して取組を進めてきました。しかし2022年2月には、ロシアによるウクライナ侵略が発生し、世界中を取り巻くエネルギー情勢は一変しました。
エネルギー分野におけるインフレーションが世界的に顕著となり、日本においても電力需給ひっ迫やエネルギー価格の高騰が生じるなど、石油危機以来のエネルギー危機が危惧される事態となりました。加えて翌年には、日本の原油の9割以上を依存する中東地域における軍事的緊張が高まり、化石燃料の調達に関する不確実性が上昇するなど、日本が抱えるエネルギー需給構造上の課題が改めて浮き彫りとなりました。
エネルギー価格は一次産品の中でも経済に与える影響が大きく、そのためロシア情勢においては、国内外で様々な政策対策等が取られ、現状においてはエネルギー価格の安定化がより強力に図られています。また、輸入に頼らないエネルギー減となる国産再エネ電力の増加は一定程度必要ではあるものの、発電量が不安定であるという大きな弱点があるため、それよりも需給調整や蓄電など再エネの弱点を克服する取り組みの重要性が増してきていると考えられます。
なお再エネ普及においては、現状では再エネ賦課金という国民負担を原資として、前述のFIT制度が牽引して市場を伸ばしております。FIT制度によって、長期的かつ高額な水準での固定価格での売電が可能となったため、再エネ電源の開発によってどの程度の利益が発生するか計算しやすくなり、結果として銀行の融資も受けやすくなりました。
ただ、FIT制度による売電価格が高額になりすぎると、結果として再エネ賦課金に跳ね返り国民負担が大きく増大することとなります。そのため、毎年「調達価格等算定委員会」によって適切な単価水準が議論され、最終的に経済産業大臣が設定しています。本記事では、2025年度以降のFIT制度および再エネ賦課金の状況について見ていきます。
再エネ賦課金は3.98円/kWh、前年度から14%増加
FIT制度は10~20年間の固定価格によって再エネ電力を売電可能な制度となりますので、制度発足から20年間となる2032年まではFIT対象発電所は増加傾向になることが想定され、基本的には単価が上がっていく事となります。買取費用は約4.8兆円となり、それに対して発電原価ともいえる回避可能費用および運営費との差額によって単価が定まります。その結果、2025年度は3.98円/kWh、前年度から14%増加となりました(図1)。

図1 再エネ賦課金単価算定根拠 出典:経済産業省
なお、下記表は制度発足からの単価推移となりますが、凡そ増加傾向にあるものの2023年度は単価が大きく下がっています(表1)。この背景には、ロシア情勢によって回避可能費用が大きく値上がったため、FITによる買取費用との差分が小さくなり、再エネ賦課金が低くなっています。そうした点では、再エネ賦課金は電力価格の上下動を一定程度抑え平準化する効果もあるものと言えます。
| 年度 | 買い取り単価 | 昨年度比 | 標準家庭の負担(300kWh/月) |
|---|---|---|---|
| 2012年度 (2012年8月分~2013年3月分) |
0.22円/kWh | – | 年額792円、月額66円 |
| 2013年度 (2013年4月分~2014年4月分) |
0.35円/kWh | 0.13円(約59%)増 | 年額1260円、月額105円 |
| 2014年度 (2014年5月分~2015年4月分) |
0.75円/kWh | 0.4円(約114%)増 | 年額2700円、月額225円 |
| 2015年度 (2015年5月分~2016年4月分) |
1.58円/kWh | 0.83円(約111%)増 | 年額5688円、月額474円 |
| 2016年度 (2016年5月分~2017年4月分) |
2.25円/kWh | 0.67円(約42%)増 | 年額8100円、月額675円 |
| 2017年度 (2017年5月分~2018年4月分) |
2.64円/kWh | 0.39円(約17%)増 | 年額9504円、月額792円 |
| 2018年度 (2018年5月分~2019年4月分) |
2.90円/kWh | 0.26円(約10%)増 | 年額10440円、月額870円 |
| 2019年度 (2019年5月分~2020年4月分) |
2.95円/kWh | 0.05円(約2%)増 | 年額10620円、月額885円 |
| 2020年度 (2020年5月分~2021年4月分) |
2.98円/kWh | 0.03円(約1%)増 | 年額10728円、月額894円 |
| 2021年度 (2021年5月分~2022年4月分) |
3.36円/kWh | 0.38円(約13%)増 | 年額12096円、月額1008円 |
| 2022年度 (2022年5月分~2023年4月分) |
3.45円/kWh | 0.09円(約3%)増 | 年額12420円、月額1035円 |
| 2023年度 (2023年5月分~2024年4月分) |
1.40円/kWh | -2.05円(約-59%)減 | 年額5040円、月額420円 |
| 2024年度 (2024年5月分~2025年4月分) |
3.49円/kWh | 2.09円(約149%)増 | 年額12564円、月額1047円 |
| 2025年度 (2025年5月分~2026年4月分) |
3.98円/kWh | 0.49円(約14%)増 | 年額14328円、月額1194円 |
表1 再エネ賦課金の推移 出典:経済産業省
2025年度以降、太陽光・陸上風力・中小水力の一部が単価変更
FIT制度における買取価格等については、再エネ特措法の規定に基づき、毎年度、再エネ電気の供給が効率的に実施される場合に通常要する費用等を基礎とし、適正な利潤等を勘案して、経済産業大臣が設定しています。
2024年度と比較すると、太陽光発電および陸上風力(リプレース除く)、中小水力の1,000kW以上5,000kW未満の区分において2025年度以降に単価が低減傾向にあります(図2)。これによって、再エネ賦課金の負担が減ることが想定される一方、再エネ事業者にとっては効率的な事業運営が求められるようになります。なお、過去の単価推移についてはFIT単価ページに整理しておりますのでご参考ください。

図2 2025年度以降の買取価格等 出典:経済産業省
特に太陽光発電については、初期投資支援スキームといった新たな仕組みが導入される見込みです(図3)。これによって、より早期の投資回収が可能となり、太陽光発電の拡大が期待できます。
初期投資支援スキームについては、「階段型の価格設定」と「支援期間の短縮」の2種類に大きく大別されます。住宅用太陽光に適用する初期投資支援スキームとしては「支援期間の短縮」が基本方針とする一方、既存のPPA事業との整合性等も考慮し、「階段型の価格設定」がまずは導入されます。ただし、2027年度以降は「支援期間の短縮」となる可能性が比較的高いものと考えられます。
一方で事業用太陽光は「階段型の価格設定」がベースとなり、2027年度以降も継続して同スキームが運用されると想定されます。
なお既存の開発案件への配慮等もあり、初期投資支援スキームは2025年度下半期より開始となります。内容としては、住宅用太陽光は最初の4年間は24円と高額売電とする一方、5~10年目は8.3円とすることで、早期での回収率が高くなります。事業用太陽光(屋根設置)は5年目までは19円、6~20年は8.3円となります。

図3 初期投資支援スキームの概要 出典:経済産業省
太陽光発電の導入量、世界では2022年から2023年に2倍近くに、日本の増加量は横ばいで堅調
太陽光発電は、FIT制度が対象とする再エネの中で最も効果を発揮し、大幅に導入拡大が進んだ類型であると言えます。理由としては、地熱や風力等と比較して、比較的に適地も多く初期リスクも小さいほか、施工可能な人員や営業者も多数いたためと考えられます。
日本では、FITの開始した2012年度は1.7GW程度の新規導入量であったものが、2014年度には5倍以上に9.4GWまで拡大し、その後2016年頃から5GW程度で横ばいで推移、ただその後2023年度には3.1GW程度となっています。徐々に新規導入量が減ってきておりますが、太陽光発電の大幅導入によって設置する適地も減っていく中、比較的に横ばいの増加量で推移しています。
そのため、今後はより効率的なパネルの開発や、ペロブスカイト型といった、これまでと異なるイノベーションが発生しない限り、徐々に新規開発量は落ち着いていく可能性が高いものと考えられます。その中で、特に太陽光発電については2024年4月1日に改正された再エネ特措法に基づき、周囲への説明会や事前周知(ポスティング等)が必要となります。これらによって、より新しい形での太陽光発電の拡大と、地域の方々への理解が共存した再エネ普及が期待されます。
一方で世界全体では太陽光発電の拡大余地が大きく、2023年の新規導入量は約407~446GWとなり、前年比で79%~96%増と急拡大しています。そのため、世界全体での新規導入量の割合で見ると、日本が占める割合は低下傾向にあります(図4)。

図4 世界と日本の太陽光発電導入実績 出典:経済産業省
太陽光発電、住宅向けはインフレ等で直近はシステム費用上昇、事業用は継続して下落傾向
近年の住宅用太陽光発電のシステム費用は、新築案件・既築案件ともにやや上昇傾向にあります。例えば新築案件について設置年別に見ると、2024年設置の平均値は28.6万円/kW(中央値28.7万円/kW)であるのに対し、2025年度の想定値は25.5万円/kWと上回っています(図5)。
2024年の増加の程度としては、2023年対比で0.3万円/kW(1.0%)、2022年設置では1.7万円/kW(6.5%)増加しています。平均値の内訳は、太陽光パネルが約47%、工事費が約29%を占め、そのほかにパワコンや架台等となります。人件費の高騰や、インフレ等の影響があるものと想定されます。

図5 住宅用太陽光発電のシステム費用の推移とその内訳 出典:経済産業省
一方で事業用太陽光発電のシステム費用については、すべての規模で低下傾向にあります。2024年に設置された10kW以上の平均値(単純平均)は22.6万円/kW(中央値は21.5万円/kW)となり、平均値は前年より1.2万円/kW(5.2%)低減しています。平均値の内訳は、太陽光パネルが約38%、工事費が約33%、残りはその他となり、パネル費用と工事費が近い水準となっています(図6)。
基本的には太陽光発電のシステム費用は、FIT開始の2012年以降の10年スパンで見ると、各社の事業努力等により徐々に低価傾向にあります。ただ、住宅用は直近では値上がり傾向にあり、太陽光パネルの価格上昇等が影響していると考えられるところ、国際市況においては、モジュール価格が低下傾向にあります。
FIT価格は、発電事業者が適切なIRRの水準で利益を得られる必要がありますが、しかし国際マーケットでもパネル価格が低下傾向であること、また自動車や家電等でも広く利用されるトップランナー水準照らし合わせること等によって、買取単価を引き下げ国民負担の軽減が図られる結果となりました。

図6 事業用太陽光発電のシステム費用の規模別の推移 出典:経済産業省
なお、FIT制度の目的の一つとしては、FIT開始の初期は国民全体で費用負担する一方で、大量導入による量産効果や、市場を担保することによって技術開発を促進し、国民負担がなくとも能動的に再エネが導入される状況を目指すものがあります。
この点で、太陽光発電は徐々にグリッドパリティを達成しつつあります。また自立化するということは、ビジネスで利益を出せるということですので、発電単価(LCOE)が環境価値を含む事業収入単価より下がることが不可欠となります。この点でJPEAによる報告書によると、2035年に向け事業太陽光(地上設置)の平均発電コストが8円/kWh程度に低減し、2030年~2035年の間には事業太陽光(地上設置)の自立化が実現すると期待されています(図7)。
また自立化に向けたステップとして、FITからFIPへの移行を推進し、電力市場への統合を進めることが極めて重要としています。発電事業者、アグリゲーター、需要家が連携し、自立化していくことで、エネルギーの在り方も新しい時代の形に変化していくものと期待されます。
なお、これらの点で直近において大きな検討事項としては、全国の低圧太陽光を数十社に集約し、「適格事業者」を認定する仕組みが有識者会議において議題となっています。現状では、50kW未満の低圧事業用太陽光が件数で8割以上、容量で約半部を占め、分散型の構造にあります。
今後、多極分散ゆえに運用管理を効率化できず、発電事業の廃棄・現象が懸念されています。そこで、エリアごとに優良な事業者が小規模太陽光を集約して、所有・管理することで効率的な運営を実現し、分散する小規模な発電事業を長期に安定電源化していくことが検討されています。筆頭としては、公平性を保ちオーソリティが高く、広域的な知名度と安心感のあるみなし小売電気事業者(各エリア大手10社)が挙げられると想定されますが、これからのエネルギー事業の新しい収益源やビジネスとして発展していく事が期待されます。

図7 事業用太陽光発電(地上設置)の自立に向けたシナリオ 出典:経済産業省
発電コストが横ばいの風力発電、運転期間の長期化やAI活用により自立化目指す
陸上風力発電について案件ごとのkWh当たりコストは、各設置年別の中央値を取ると、凡そ10円台で推移しています。また、各案件のkWh当たりのコストをプロットすると、案件ごとのばらつきは大きいものの、8円/kWh付近のコストで事業を実施できている案件もあります。ただし、FTI開始の2012年から2023年まで10年以上が経過していますが、コストは凡そ横ばいであり、価格低減が進んでいる太陽光発電と大きく異なります(図8)。

図8 陸上風力発電のkWh当たり発電コスト 出典:経済産業省
その一方でFITによる単価は陸上風力発電が14円/kWh(2024年度入札における上限価格)、着床式洋上風力発電(再エネ海域利用法適用外)が24円/kWh(2024年度)で設定されていますが、、海外の買取価格と比べて高い傾向にあります(図9)。

図9 風力発電(20,000kW)の各国の買取価格等 出典:経済産業省
今後のコスト低減に向けては、一般社団法人日本風力発電協会が資料をまとめており、「コスト面の自立化に向けた取り組みは不断に進められているものの、物価高騰・円安等を始めとする外部要因の悪化に伴い、取り組みの効果が打ち消されている現状」としています。
その他にも、建設業界の人手不足・高齢化の問題が顕在化し、働き方改革の影響もあり、工期の長期化、立地制約による規模縮小、出力制御量の増加、系統整備の長期化といった要素もあり、課題が多くあります。
その一方で、風車出力規模の大型化。風車ハブ高の伸長、風車ローター径の伸長といった「大型化」が対策の一つとなるとしています。そのほか、ウィンドファーム認証の審査期間の短縮、国内SEP船等の新造、施工及び操業の習熟化等によって資本費を抑えられる道筋が立てられています。運転維持費は、弱風時での定期点検の実施、AI技術開発によるO&Mの合理化等によって効率化し、運転期間を25年から35年に延長することで全体コストを抑える対策が検討されています(図10)。

図10 風力発電のコスト面自立化に向けた取組イメージ 集計
大規模な洋上風力発電、物価変動に合わせた価格調整スキームによって事業リスク低減
大規模な洋上風力に関しては、2024年9月に開催された「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」において、電源投資が確実に完遂されるようにするため、収入・費用の変動に対して強靱な事業組成を促進することを通じて、事業実施の確実性を高めていく方向性が示されています。
それを受けて「洋上風力促進WG・洋上風力促進小委員会合同会議」では、再エネ海域利用法の制度見直しの方向が取りまとめられました。この制度見直しには、①保証金に関する事項(撤退や遅延を抑止する保証金制度の見直し)や、②基準価格/調達価格に関する事項(電源投資を確実に完遂させるための価格調整スキームの導入)が含まれています。
保証金に関しては、諸外国(デンマーク、オランダ、ドイツ)における最新の保証金額の平均を日本の第3次保証金額として設定し、第2次保証金額も併せて変更することとなりました。また、併せて、大きな遅延を抑止する観点から、迅速性評価の点数が下がる半年毎に順次保証金を没収し、2年以上の遅延で全額没収することとなります。具体的には、維持保証金が500円/kW、2次保証金が10000円/kW、3次保証金が24000円/kWとなります(図11)。

図11 大型養生風力の撤退や遅延を抑止する保証金制度の見直し 出典:経済産業省
価格調整スキーム、大規模な洋上風力発電に価格調整スキームを導入している国としては初の試みとして下限を導入
大規模な洋上風力の開発は、費用も巨額で工期も長くなることから事業リスクが非常に高く、価格調整スキームが適用されます。価格調整スキームは、民間事業者のみでは取り切れない物価変動リスクを、制度側で引き受けるという仕組みとなります。
理由としては、大規模な洋上風力発電については、①投資額が大きく総事業期間も長期間となることや、②サプライチェーンの混乱、インフレによる開発費用の増大等により、海外において大規模な洋上風力プロジェクトからの撤退事例が複数生じていること等から、収入・費用の変動リスクへの対応が可能なスキームとして導入されることとなりました。
価格調整スキームの特徴的な部分としては、物価変動率に合わせたIRRの設定が設けられる部分にあります。ただし物価変動率については際限なく調整される訳ではなく、上下限が設定されます。
上限については、仮に2024年4月を公募占用計画に記載された洋上工事日が属する月とした場合、変動後物価指数として参照するのは2023年度となり、変動前物価指数として参照するのはおおよそ2018年度と想定されます。これを踏まえ、変動前の2018年度と変動後の2023年度を比較すると、約+40%の物価変動が見られます(図12)。
この物価変動率については、ウクライナ危機による世界的な物価上昇や急激な円安に伴う影響も含まれていることから、十分な物価変動リスクを織り込んだ水準と評価できるため、物価変動率の上限は、当該水準(40%)を基本と設定されました。ただし今後、価格調整の上限を40%に設定すると過度な国民負担が生じると判断された場合には、40%未満の水準を採用し、公募占用指針に明記することなります。

図12 2018年度を基準とした物価指数の推移 出典:経済産業省
一方で下限値については、足元における洋上風力発電事業の実態等を踏まえつつ、1%から開始することとなっています。この下限値設定は、洋上風力発電に価格調整スキームを導入している国としては初の試みとなります。
ただし、下限値も上限値と同様に、今後見直しが継続して検討されていく見込みです。例えば、日本における洋上風力事業者の資金調達コスト(中間は概ね4%、最大値は概ね5%)とIRR(5~6%)の差(1%)をリスクプレミアムとして想定し、当該リスクプレミアムに対し、価格調整が必要な期間(公募から洋上工事開始までの5年間程度)を乗じた5%を、下限の水準として目指していくことが検討されています。
また一方、短期間で下限の水準を急激に引き上げることは事業性への影響が大きい可能性があることを踏まえ、2026年度の調達価格等算定委員会においては、国内の1年間における物価安定目標の水準やIMFによる日本の物価変動率見通しも参考に、下限の水準を2%に引き上げることについて検討が進められる見込みです。
地熱発電、2035~2040年を努力目標にコストを約10%減
FIT制度における地熱発電の買取価格等は、設備類型の詳細化等はあるにせよ、制度開始から凡そ横ばいで推移しています。基本的には、容量の増加に応じて価格が連続的に変化する「フォーミュラ方式」による価格設定が基本となっています(図13)。
また30,000kWの設備規模の地熱発電を参照すると、新設の場合は26円/kWhとなり、例えば地熱発電発祥の地となるイタリアと比較すると2倍以上の価格となっています。

図13 地熱発電(30,000kW)の各国の買取価格 出典:経済産業省
その一方で、FITによる買取期間は基本は15年間となりますが、地熱発電は長期稼働が見込まれる電源であり、50年以上の長期間操業が期待される電源となります。また実態としても、50年程度運転を継続した地熱発電所は日本に複数存在しています。
そのため、FIT期間後の方が長い期間の稼働が見込まれることからも、地熱発電は自立化へのステップとして、早期に電力市場へ統合していくことが適切とされています。
なお、30,000kWをモデルケースとした直近の価格情報を反映した発電コストは19.1円/kWhとなります。
これに対し、建設に関するコスト低減実施(①掘削費減、②坑井能力向上、③地上設備建設費減)により17.7円/kWh(7.1%減)、さらに操業に関するコスト低減(利用率向上、操業費低減)を追加で実施することで17.1円/kWh(10.4%減)となることが見込まれています(図14)。日本地熱協会によると、2035~2040年に努力目標としてこれらのコスト低減を行うものとしています。

図14 地熱発電のモデルケースによるコスト低減効果の試算 出典:経済産業省
中小水力はほぼエネルギーミックスの導入量を達成、FIT後の長期的な運用が鍵に
中小水力発電については、2030年エネルギーミックス(1,040万kW)の水準に対して、2024年3月末時点のFIT前導入量+FIT・FIP認定量は1,030万kW、導入量は1,000万kWと凡そ目標を達成しているボリュームが開発されています。
なお、FIT制度における2024年度の調達価格・基準価格は、200kW以上1,000kW未満で29円/kWhなどですが、海外の買取価格と比べて高い傾向にあります(図15)。こうした制度の後押しもあり、中小水力は順調に導入量が進展しているものと考えられます。

図15 中小水力発電(200kW)の各国の価格 出典:経済産業省
なお水力発電は歴史が長く、技術的にも確立されていた発電類型です。これまで多方面にわたるコスト低減が進められており、技術革新による大幅なコスト低減は簡単ではない状況と言えます。
一方、水力発電は建設時の初期投資費用が大きいものの、耐用年数を過ぎても改修等を行うことで恒久的に活用することができます。このことからFIT/FIP制度を活用し、初期段階で投資費用を回収することで、FIT/FIP制度期間終了後については競争電源として長期にわたり自立していくことが可能な電源と言えます。そのため地熱発電と同様に、早期に電力市場へ統合していくことが適切と考えられる電源と考えられます。
ただ足元環境での発電コストは、1,000kWクラスの流込式区分でLCOE(60年平均)13.4円/kWhとなり、自立化のためには9.2円/kWh程度の水準まで引き落とすことが必要とされています(図16)。13.4円/kWhから9.2円/kWhにするためには約31%のコストダウンが必要となり、自立化のためには例えば、運用による発電電力量の増加(計画停止の最小化、計画外作業停止の極小化、増電力の取組み)や維持管理費の削減(ドローン活用等のスマート保安導入)等のコスト削減が今後必要になってくると想定されます。

図16 水力発電のコスト面での自立化に向けた取組み 出典:経済産業省
バイオマス発電は既にエネルギーミックスの目標量を達成、コスト削減難しく地域との共生や高付加価値での販売が重要
バイオマス発電については全体で1,070万kWとなっており、既に2030年エネルギーミックスの水準(800万kW)を超えている電源となります。そのため、目標導入量としては既に達成している電源となっています。
また、2024年度の調達価格・基準価格は、入札対象外の一般木材等(10,000kW未満)では24円/kWhであり、海外と比較すると高い水準であると言えます(図17)。また日本のFITでは一般木材等(10,000kW以上)は入札対象となっていますが、海外では大規模な一般木材等バイオマスは、支援対象でない場合もあります。

図17 バイオマス発電(5,000kW、ペレット使用)の各国の価格 出典:経済産業省
バイオマス発電は電源の性質上、再エネとしては珍しく発電コストの大半を燃料費が占めるというコスト構造にあります。また大規模バイオマスについては、国際市場の需給や円安等の影響を強く受ける性質もあり、他の再エネ電源と比べ、どうしても単価が高くなりがちであり、再エネ電源としての自立化が相対的に難しい発電類型です。
またバイオマスは燃料によっては、森林破壊などを進めてしまう可能性もあります。そのため、FIT利用においては第三者認証の取得が必要となります。またバイオマスは再エネの中でも特殊な類型であり、例えば東京都のキャップ&トレードにしても、再エネ電力の内バイオマス燃料については、他の再生可能エネルギーと異なり特殊なルールが適用されます。大枠としては、持続可能性(ライフサイクルGHGの最小化や資源の安定的な確保や調達)の担保が必要となってきます。
またバイオマスは一度建設したらその後はメンテナンスするだけはなく、燃料を入れ続ける必要があります。こうしたことから、前述の通りで発電原価を引き下げづらく、各地域の林業や畜産業等といった地域との連携が必要な電源であると考えられます。そうした付加価値を生み出し、バイオマスの再エネ価値をより高く評価する需要家獲得を目指すことが必要となります。バイオマス発電事業者協会の資料によると、2040年頃には約12~20/kWhの発電原価を目指し、約17~23円/kWhで売電する収益モデルが想定されています(図18)。

図18 バイオマス発電の卒FIT後の発電原価想定と自立化について 出典:経済産業省
この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。
無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです
執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター
EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。
| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |
|---|---|
| 所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |
| 電話番号 | 03-6411-0859 |
| 会社HP | http://eic-jp.org/ |
| サービス・メディア等 |
https://www.facebook.com/eicjp
https://twitter.com/EICNET |
関連する記事はこちら
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年10月29日
前編では、ペロブスカイト太陽電池の特性と政策的背景、そして中国・欧州を中心とした世界動向を整理しました。 中編となる今回は、社会実装の要となる耐久性・封止・量産プロセスを中心に、産業戦略の現在地を掘り下げます。ペロブスカイト太陽電池が“都市インフラとしての電源”へ進化するために、どのような技術と制度基盤が求められているのかを整理します。特に日本が得意とする材料科学と製造装置技術の融合が、世界的な量産競争の中でどのように差別化を生み出しているのかを探ります。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年10月27日
中小企業が入れるRE100/CDP/SBTの互換ともいえるエコアクション21、GHGプロトコルに準じた「アドバンスト」を策定
GHGプロトコルに準じた「エコアクション21アドバンスト」が2026年度から開始される見込みです。アドバンストを利用する企業は電力会社の排出係数も加味して環境経営を推進しやすくなるほか、各電力会社側にとっても、環境配慮の経営やプランのマーケティングの幅が広がることが期待されます。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年10月18日
日本発!次世代ペロブスカイト太陽電池:フレキシブル発電が都市を変える 【第1回】背景と技術概要 — 何が新しいか/政策・投資の全体像/海外動向との比較
本記事は、2024年公開の「ペロブスカイト太陽電池の特徴とメリット」「ペロブスカイト太陽電池の課題解決と今後の展望」に続く新シリーズです。 耐久性や鉛処理、効率安定化といった技術課題を克服し、いよいよ実装段階に入ったペロブスカイト太陽電池。その社会的インパクトと都市エネルギーへの応用を、全3回にわたって取り上げます。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年10月17日
非化石証書(再エネ価値等)の下限/上限価格が引き上げ方向、脱炭素経営・RE100加盟の費用対効果は単価確定後に検証可能となる見込み
9月30日の国の委員会で、非化石証書の下限/上限価格の引き上げについて検討が行われています。脱炭素経営の推進を今後検討している企業等は、引き上げ額が確定した後にコスト検証を実施することが推奨されます。また本記事では、非化石証書の価格形成について内容を見ていきます。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年09月29日
【第3回】電力小売に導入が検討される「中長期調達義務」とは ——料金・市場構造・投資への影響と導入後の論点—
第1回では制度導入の背景を整理し、第2回では設計の仕組みと現場課題を取り上げました。最終回となる本稿では、中長期調達義務が導入された場合に、料金や市場構造、投資意欲にどのような影響が及ぶのかを展望します。
制度の目的は電力の安定供給を強化し、価格急騰のリスクを抑えることにあります。ただし、調達コストの前倒し負担や市場流動性の低下といった副作用も想定されます。今後は、容量市場や需給調整市場との整合性、データ連携による透明性、新規参入環境の整備といった論点への対応が、制度の実効性を左右することになります。