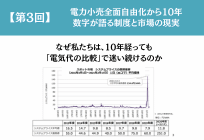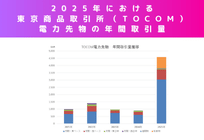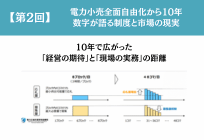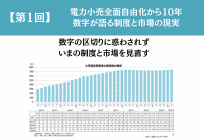6月から観光客の受け入れ開始!観光業界にも広がる脱炭素の波とは
| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |
一般社団法人エネルギー情報センター

6月から日本でも観光目的の外国人の受け入れが開始しました。コロナにより需要が激減した観光産業の復活に期待が寄せられています。一方で、コロナ禍で急速に進んだ脱炭素化の流れは観光産業にどのような影響を与えているのでしょうか。そこで今回は、観光産業の脱炭素関連の動向を整理し、すぐできるエネルギーの見える化や今後の観光のあり方について考えていきます。
日本が観光地としての魅力度、初の世界1位に!
6月10日を皮切りに、段階的に観光客の受け入れが開始されました。約2年ぶりということもあり、落ち込んだ観光需要、インバウンド需要を盛り上げようというムードが日本でも広がっています。
世界経済フォーラム(WEF)が発表した2021年版の旅行・観光開発ランキングで、日本は交通インフラの利便性や自然や文化の豊かさなどが評価され、総合順位では調査の開始以来、初めて世界1位になりました。これは観光地としてどれだけ魅力的か、各国の競争力を比較した世界的な調査結果だということです。
観光庁の旅行・観光消費動向調査によると、2021年の旅行・観光消費額は9兆1,215億円で、2019年の21兆9,312億円からは58.4%減と半減しているのが現実です。そのため、外国人の観光客受け入れ開始のニュースやこうした世界的な日本での観光に対する高評価は、非常に期待感が高まります。
観光業界にも脱炭素の波
一方で、コロナを機に世界中で脱炭素の流れが強まりました。その波は観光業界にも押し寄せています。
ホテルなど宿泊施設やレジャー施設であれば「グリーンキー」や、ツアー事業者や旅行会社だと「トラベライフ」といった、サスティナブルな国際的認証制度があります。場合によっては、それらを取得していないと海外の旅行会社と取引できないという足切りに合うような状況も出てきています。
グリーンリカバリーを掲げ、脱炭素への取り組みが先進的なヨーロッパでは「飛び恥」が大きな話題となりました。飛び恥とは、フライトシェイム(Flight Shame)と訳されます。二酸化炭素の排出量の多い航空機の利用を避けようとする運動のことです。飛行機に乗ること自体が、CO2排出の影響が非常に大きく、ヨーロッパの人々が日本にくることのハードルが高くなっているという指摘があります。

脱炭素時代における観光産業の取り組み
そのような脱炭素時代において、いくつかのアイディアがあります。
まずは、直近では、飛行機の移動ではCO2は出してしまうものの、それ以降の日本での交通はCO2フリーにしていくこという方法です。移動するのは仕方がないにしてもそれを日本国内でオフセットできるようなプラン(ツアー)が出来ないかという考え方です。海外の方も罪悪感なく日本に来れて、旅行が盛り上がるという発想です。
例えば、旅行先として環境省で取り組む「ゼロカーボン・パーク」があります。ゼロカーボン・パークとは、国立公園における電気自動車(EV)等の活用、国立公園に立地する利用施設における再生可能エネルギーの活用、地産地消等の取組を進めることで、国立公園の脱炭素化を目指し、サステナブルな観光地づくりを実現していくエリアのことです。

セロカーボンパーク イメージ図 出典:内閣官房HP 地域脱炭素ロードマップ(概要)
旅行代理店各社も、旅行やイベントで排出するCO2の削減を目指した商品開発に相次いで乗り出しています。このようなツアーを積極的に活用してもらうという方法もあります。
例えば、日本旅行は個人を対象とした国内旅行商品で「カーボンオフセット」のプランを2月から販売している。JRを使って実際に移動した距離からCO2排出量を計算。それに見合う排出権分の金額を旅行者が支払う代金に上乗せするというものです。
また、航空業界も動いています。先の話にはなりますが、ANAでは持続可能な航空燃料(SAF)の導入によって2050年度までに航空機の運航によるCO2排出量実質ゼロを掲げています。
そうした航空業界の動きもあり、「スカイスキャナー(Skyscanner)」という航空券予約サイトでは、チェックボックスをつければCO2の排出量が少ないルートや航空会社が出てくるなどの仕組みを提供しています。こうした業界の枠を超えた観光ビジネス全体での脱炭素化への動きはますます加速しそうです。
すぐにできるエネルギーの見える化と今後の観光の在り方
では、中小企業も多いとされる観光産業に関わる企業がまずできることとして何があるのでしょうか。
まずは、エネルギーやCO2排出量に関する見える化です。今までなんとなく使っていたエネルギーを見える化してみると、だれもいないところで照明がついていたなどの非効率な部分や無駄な部分、エネルギーの調達の仕方を見直せたといったことがあります。その結果、全体のエネルギーコストを下げることができます。
例えば電気代が数百万~数千万円かかっているような企業の場合、その1割~1.5割削減できると、数十万~数百万円の削減になります。そこで削減浮いた分の費用を脱炭素戦略に回すことができます。
ではどのような脱炭素戦略があるのか、そのヒントになる先進的な事例として以下をご紹介します。
◆ヒルトン、米国初の「ネットゼロホテル」開業
米コネチカット州で2022年5月に「ホテル・マルセル・ニューヘイブン タペストリー・コレクション・バイ・ヒルトン」が開業しました。敷地内での太陽光発電で客室や宴会会議施設、パブリックスペース、レストラン、ランドリーなどで使用するエネルギーを生み出すことで、米国のホテルで初めて「ネットゼロ」を実現しています。

出典:ヒルトンHP
◆ホテルグレートモーニング博多
国内では2020年8月に、ホテルグレートモーニング博多がホテルで使用する全ての電気を自然エネルギー由来の電気に切り替えました。環境に配慮した滞在が可能になり、年間約2900本分の杉の木に相当するCO2が削減できる見込みです。
このように、ホテルや旅館をやられていて場所があるところは、再生可能エネルギー、太陽光発電からやってみることもひとつです。また、限定的ですが、温泉街であれば、地熱発電に取り組んでみるといったアイディアもあるでしょう。
その他にも、場所がなくても再エネの権利を買ってくるなどして、CO2フリーな商品を作ってみるといった取り組みがあります。SAKE RE100というプロジェクトです。
◆SAKE RE100
海外で日本酒人気が広がり、「Sake」ということばが定着し始めたことで、観光産業に一役買っている日本酒。SAKE RE100は、全国に約1,300ある酒蔵の99%近くを占める小規模酒蔵が、再エネ導入へ踏み出すきっかけを作り、再生可能エネルギーを使った酒造りによって、日本酒(SAKE)の力でCO2削減を目指すものです。
※RE100とは、企業が自らの事業の使用電力を100%再エネで賄うことを目指す国際的なイニシアティブです。
最後に、政府の後押しをうまく活用するということについて触れておきます。先述の「ゼロカーボン・パーク」以外にも、政府の施策として「グリーンライフポイント」や、「脱炭素選考地域」といった取り組みがあります。また、各種補助金なども様々出ています。
観光産業に携わる企業や観光業が産業のメインである自治体はこのような流れをうまく活用して、環境に優しい旅行のPRに活用していけると良いのではないでしょうか。
この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。
無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです
執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター
EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。
| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |
|---|---|
| 所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |
| 電話番号 | 03-6411-0859 |
| 会社HP | http://eic-jp.org/ |
| サービス・メディア等 |
https://www.facebook.com/eicjp
https://twitter.com/EICNET |
関連する記事はこちら
一般社団法人エネルギー情報センター
2026年02月11日
電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第3回】なぜ私たちは、10年経っても「電気代の比較」で迷い続けるのか
電力小売全面自由化から10年が経過し、電気料金のメニューや契約形態は大きく多様化しました。 一方で、どの電気契約が有利なのかという問いは、いまも多くの現場で解消されないまま残っています。 見積書を並べ、単価を比較し、条件を読み込んでも、最後の判断に踏み切れない。こうした迷いは、単なる理解不足や情報不足として片づけにくいものになっています。 判断が難しくなる背景には、情報の量ではなく、比較に持ち込まれる情報の性質が揃わなくなったことがあります。 単価のように「点」で示せる情報と、価格変動や運用負荷のように時間軸を含む「線」の情報が、同じ比較枠の中で扱われやすくなっているためです。 本稿では、この混線がどこで起きているのかを整理します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2026年01月19日
2025年の電力先物市場:年間取引量4,583GWhで過去最高更新、年度物導入と中部エリア上場を控えた市場の変化
価格変動リスクへの対応を意識した取引行動が、実務レベルで具体化し始めた一年となりました。 制度面では年度物取引の導入、取引環境では流動性改善やコスト低減策が進み、企業側では中長期のヘッジ設計を見直す動きが重なりました。こうした複数の要因が同時に作用した結果、東京商品取引所(TOCOM)における電力先物の年間取引量は約4,583GWhと、前年比約5倍に拡大し、過去最高を更新しています。 中でも、東エリア・ベースロード電力先物が前年比約5倍、西エリア・ベースロード電力先物が前年比約3倍と伸長し、主要商品の取引が全体を押し上げた形となりました。加えて、2025年5月に取引を開始した年度物取引も、市場拡大を牽引する要素となっています。 本稿では、2025年通年の動向を中心に、市場拡大の背景と今後の論点を整理します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2026年01月19日
電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離
「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年12月31日
電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す
「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年12月27日
政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略
これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。