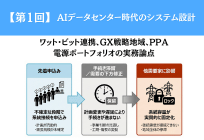系統用蓄電池の導入事例について|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ
| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |
一般社団法人エネルギー情報センター

2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、株式会社パワーエックスの小嶋 祐輔 氏が講演した「系統用蓄電池の導入事例」について、その要約をご紹介します。
PowerXについて
PowerXは、「永遠に、エネルギーに困らない地球」をビジョンに掲げています。 そして、その実現に向けたミッションとして、「自然エネルギーの爆発的普及を実現する」という目標を2030年までに達成することを目指しています。次世代のエネルギーカンパニーとして、蓄電池の製造にとどまらず、それをどのように活用するのか、特に再生可能エネルギーのさらなる普及にどうつなげていくのかを考えながら事業を展開しています。
PowerXと聞くと、多くの方が電気運搬船のイメージを持たれるかもしれません。しかし、電気運搬船事業は「海上パワーグリッド」という別会社を設立し、PowerXとは独立した資金調達のもとで運営しています。この事業は他の事業と比べて、より長期的な視点で取り組んでいます。現在、PowerXの事業は主に3つの柱で成り立っています。一つは蓄電池の製造・販売を中心とした事業、もう一つはEVステーション事業、そして最後の一つが電力事業です。蓄電池事業では、単に製造・販売するだけではなく、それをどう活用していくかが重要になります。特に、系統用蓄電池においては最適な運用支援も行いながら、「メイド・イン・ジャパン」の技術を活かし、日本発の蓄電池製造基盤を確立することを目指しています。また、EVステーション事業では、急速充電器付きの蓄電池を販売し、店舗展開を進めています。再生可能エネルギーと電気自動車の普及を加速させるために、充電インフラの整備は欠かせません。
PowerXはその一翼を担うべく、エネルギーとモビリティをつなぐ新たなソリューションを提供していきます。これまでの累計資金調達額は259.2億円に達しています。商社、電力会社、金融機関など、さまざまな企業からご支援をいただいており、単なる投資ではなく、ビジネスモデルや可能性に共感し、期待を寄せてくださっていると感じています。
蓄電池製造工場について
PowerXの蓄電池は、国内で製造しています。現在、岡山県玉野市に自社工場「Power Base」と提携工場を構え、用途に応じたさまざまな蓄電池を生産しています。
Power Base(自社工場)では、EV急速充電器付きの蓄電池「Hypercharger」、中型蓄電池「PowerX Cube」、そして水冷モジュールを製造しており、現在の生産能力は3.9GWhとなっています。
この工場では、EVインフラの普及を支えるとともに、より効率的なエネルギー管理を可能にするソリューションを提供するための製品開発を進めています。一方、岡山提携工場では、系統用蓄電池「Mega Power」を製造しており、生産能力は1.3GWhです。蓄電池のモジュール自体は、中国サプライヤーから調達していますが、それを日本国内の工場でコンテナに組み上げ、自社開発のBMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載することで、高品質な蓄電システムを提供しています。2024年から系統用蓄電池の出荷を開始し、全国10カ所の高圧蓄電所に約50台が設置されています。
製品について
PowerXでは、用途に応じたさまざまな蓄電池製品を開発・提供しています。現在、主力となる製品は、「Hypercharger」、「PowerX Cube」、「Mega Power」、そして新たに開発を進めている「Mega Power JP」の4種類です。「Hypercharger」は、蓄電池型の超急速EV充電器で、EVインフラの普及を加速させる製品です。充電インフラの不足が課題とされる中、再生可能エネルギーと組み合わせた充電ソリューションとして、持続可能なエネルギー活用を推進しています。
「PowerX Cube」は、商業施設向けの定置用蓄電池で、オフィスビルや商業施設のエネルギー管理に活用されています。電力のピークカットや非常時のバックアップ電源としての役割を果たし、エネルギーの安定供給に貢献しています。
「Mega Power」は、コンテナ型の定置用蓄電池で、系統用蓄電所向けに開発された製品です。標準サイズは20フィートのコンテナで、重さは約30トンにもなります。そのため、搬入や設置時に地盤の強度や輸送手段の制約が生じることがありました。この課題を解決するために新しく開発したのが、「Mega Power JP」です。10フィートサイズのコンテナ型蓄電池で、従来のMega Powerよりも軽量化されており、搬入や据え付けがより容易になっています。これにより、設置場所の制約を減らし、より柔軟に系統用蓄電所へ導入できるようになりました。
PowerXは、日本国内で蓄電池を製造するメーカーとして、「エネルギーインフラの安全性」 を最も重要視しています。蓄電池は、電力システムの根幹を支える重要な設備であり、国内でのメンテナンスや技術支援が迅速に行えることが、安定供給のためには不可欠だと考えています。特に、システムのブラックボックス化や外部からの制御が及ぶことは、安全保障上のリスクとなります。PowerXでは、日本国内の厳格なセキュリティ基準のもとで制御システムを開発し、遠隔監視を可能にしています。海外や外部からの不正アクセスや攻撃、乗っ取りのリスクを防ぐため、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドのすべてのレベルで強固なセキュリティ対策を実施しています。こうした技術開発は、社内で行っており、制御システムやハードウェアの独自開発を進めることで、より安全性の高い蓄電池を提供しています。
系統用蓄電所向けパッケージ
PowerXでは、高圧蓄電所のパッケージ提供を行っています。単に蓄電池を導入するだけでなく、設計・制御・運用までをトータルでサポートすることで、スムーズな導入と長期運用を実現しています。PowerXが提供する高圧蓄電所パッケージには、次の4つの特長があります。
1.必要なシステムをパッケージで提供
高圧蓄電所の設置に必要な機器やシステムを、すべてセットで提供するため、設計や導入がスムーズに進みます。
2.セキュリティ対策万全の制御設計
先ほど述べたように、PowerXは独自の制御システムを開発し、セキュリティ面でも強固な対策を講じています。遠隔監視機能も充実しており、外部からの不正アクセスや攻撃を防ぐ仕組みを備えています。
3.各種申請・法令対応のサポート
系統用蓄電所の設置には、電力会社との連携や、法令に基づいた申請が必要になります。PowerXは、これらの手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供し、円滑な導入を支援しています。
4.国産システムによる20年間の安心サポート
日本国内で製造・管理されるシステムを採用しており、長期間にわたって安定した運用が可能です。万が一のトラブル時にも迅速に対応できる体制を整えています。
加えて、系統用蓄電所を設置する際には、周辺環境への影響も十分に考慮する必要があります。特に、条例やハザードマップの確認、さらに騒音対策が重要なポイントです。蓄電所の運用には冷却ファンや変圧器などが稼働するため、音の問題が発生する可能性があります。そのため、状況に応じて防音壁をセットで設計することもあります。一般的には、周辺の民家から100メートル以上の距離を確保するのが望ましいとされています。また、系統連系のスケジュールや負担金の額も事前に把握し、導入計画を立てることが重要です。電力会社との調整には時間がかかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュール設定が求められます。PowerXでは、これらの課題にも対応できるよう、設置計画の初期段階から綿密な調査・設計を行い、最適なソリューションを提供しています。
系統用蓄電池の開発・運用スキーム
系統用蓄電所のビジネスにおいては、「開発」と「運用」は一体だと考えています。ただ蓄電池を設置するだけではなく、適切に運用し、エネルギー市場の中で最大限の価値を生み出すことが重要です。まず、開発段階では、以下のプロセスを丁寧に進める必要があります。
・事業用地の選定:適切な土地を確保するため、用地選定、地権者との交渉、地盤調査、周辺環境の確認を実施します。
・電力系統の確認・申請:事前調査を行い、接続の検討・申請から本申し込み、接続工事の負担額の確定までを進めます。
・資機材の確保:定置用蓄電池のほか、PCS(パワーコンディショナー)、変圧器、受変電設備、ケーブルなど、必要な機器を確保します。
・設置工事の実施:法令を確認しながら、基礎工事、電気工事、設置工事を適切に進めます。
これらのステップを経て、蓄電所が完成した後は、市場での取引や小売事業者との連携を考えながら、運用の最適化を行うことが求められます。運用段階では、次のような業務が重要になります。
・メンテナンス・運営:定期点検や監視、主任技術者による管理、報告業務などを含むアセットマネジメントを実施し、長期的な安定稼働を確保します。
PowerXは、これらの開発から運用までをパッケージとして提案し、一貫したサポートを提供しています。単に蓄電池を販売するのではなく、「蓄電所を建設し、建売として提供し、その後の運用も引き受ける」 というスキームを採用しています。具体的には、オーナー(事業者)に蓄電池を保有してもらい、そこからリターンを得られる仕組みを構築しています。PowerXは、蓄電所アグリゲーターとして、オーナーから運用を委託され、最適な運用を行うことで収益を生み出し、それをオーナーへ還元する形をとっています。
系統蓄電所の運用方法
系統蓄電所の運用方法として3つの選択肢を提案しています。それぞれの方法には異なるリスク・リターンの特性があり、事業者のニーズや投資方針に応じた最適な運用プランを選択することが可能です。
(1) 電力小売:低リスク・安定収益モデル
最も安定した運用方法として、電力小売と一体化した蓄電所の運用があります。これは市場価格のボラティリティに左右されず、事業性を確立できるモデルです。「X-PPA」 という電力小売サービスを提供しており、電力需要家に蓄電能力を提供する仕組みを構築しています。これにより、蓄電所の利用料を基本料金の一部として安定的に回収することができます。このスキームはすでに導入されており、日本郵政岡山局、三菱UFJ銀行、野村不動産 などが供給先として利用しています。
(2) 蓄電能力の融通:調整力を提供するモデル
この方法では、電力事業者向けに蓄電所の調整力を提供し、その対価として安定した利用料を回収します。具体的な活用例として、以下のような運用が可能です。
– 太陽光発電の夜間シフト:昼間に余剰となる再生可能エネルギーを蓄電し、夜間に供給。
– JEPX(日本卸電力取引所)の価格差を活用した裁定取引:安い時間帯に充電し、高い時間帯に放電。
– インバランス対応:電力需給のズレを調整し、電力システムの安定化に貢献。
– 調整力市場への参加:電力需給バランスを保つために、系統運用者に対して調整力を提供。
このモデルは、市場価格に左右される要素がありながらも、比較的安定した収益を得ることが可能です。
(3) 市場運用:ハイリスク・ハイリターンのダイナミックな運用
市場の動向を活用し、最大の収益を狙うのが「市場運用型」のモデルです。
– kWh取引、kW取引、ΔkW取引 などを用いたマネタイズ戦略を展開。
– 容量市場、需給調整市場、卸電力市場 などを活用し、収益を最大化。
この方法では、市況の変動に大きく依存するためリスクは高いものの、適切な運用を行えば大きなリターンを狙うことも可能です。
事業者の投資方針やリスク許容度に応じて、「低リスク・ミドルリターン」から「ハイリスク・ハイリターン」までの幅広い運用方法を提供しています。運用先の保有者様の志向に合わせ、最適な運用方法を選択し、最大限の収益を確保できるようサポートしていきます。
高圧系統蓄電所の経済性と投資モデル
エネルギーインフラ事業として成立する水準の経済性を確保した上で、高圧系統蓄電所の投資モデルを設計しています。投資回収の見込みや運用戦略に応じて、主に2つの運用モデルを提案しています。
1. トーリング型(低リスク・安定収益モデル)
– 電力小売(X-PPA)と調整力販売を中心に運用し、余剰分のみ市場運用を行うモデル。
– 市場価格の変動リスクを抑えながら、安定した収益を確保する仕組み。
– 想定収入(20年間)約10億円、想定PJ-IRR(20年評価)約4%。
2. マーチャント型(高リスク・高リターンモデル)
– すべて市場運用に特化し、市場価格の変動を活用して最大限のリターンを狙うモデル。
– 市場価格の動向に左右されるが、適切なタイミングでの取引により高収益を実現可能。
– 想定収入(20年間)約11~15億円、想定PJ-IRR(20年評価)約4~10%
投資コストと維持管理費
– 設備投資額:約5~6億円
– 維持管理費(20年間):約2.3億円
これらのコストを考慮した上で、長期的に安定したリターンを得ることを前提に設計されています。現在までリース会社や金融系の企業 に採用されています。今後も多様な事業者と連携しながら、系統蓄電所の設置と運用を促進し、エネルギーインフラの安定供給に貢献していきます。
※本サイトの内容は情報提供を目的としており、蓄電所への投資勧誘を行うものではありません。内容の正確性・将来性について株式会社パワーエックスは保証しません。
「系統用蓄電池の導入事例について」講演アーカイブ
系統用蓄電池ビジネス参入セミナーその他の講演について
・系統用蓄電池ビジネスの最前線
株式会社AnPrenergy 代表取締役 村谷 敬 氏
・系統用蓄電池のアグリゲーションについて
デジタルグリッド株式会社 代表取締役 豊田 祐介 氏
・系統用蓄電池の導入事例について
株式会社パワーエックス 執行役 電力事業領域管掌 小嶋 祐輔 氏
・系統用蓄電池での安全面や各種補助金について
電気予報士 伊藤 菜々 氏
運営事務局 おすすめの系統用蓄電池ビジネス教材
系統用蓄電池の購入・販売をご検討している事業者様へ
系統用蓄電池ビジネス参入のご相談
Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター
EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。
| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |
|---|---|
| 所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |
| 電話番号 | 03-6411-0859 |
| 会社HP | http://eic-jp.org/ |
| サービス・メディア等 |
https://www.facebook.com/eicjp
https://twitter.com/EICNET |
関連する記事はこちら
一般社団法人エネルギー情報センター
2026年01月12日
【第1回】AIデータセンター時代のシステム設計:ワット・ビット連携、GX戦略地域、PPA・電源ポートフォリオの実務論点
データセンターは、地域の電力インフラ設計を左右する存在へと変わりつつあります。背景には、需要施設の増加や、高負荷率・増設前提という運用特性に加え、脱炭素の要件も加わり、結果として、電力の「量」だけでなく「確実性」と「環境価値」が事業の成否を分ける事が挙げられます。
こうした状況の中で、日本でも制度設計が大きく動いています。具体的には、系統用蓄電池における系統容量の「空押さえ」問題に対して規律強化が議論される一方、国としてはワット(電力)とビット(通信)を一体で整備する「ワット・ビット連携」を掲げ、自治体誘致やインフラ整備を含めた「GX戦略地域」等の枠組みで、望ましい立地へ需要を誘導しようとしています。さらに、需要家側では、脱炭素要請の高まりを受けて、PPAなどを通じた環境価値の調達や、電源ポートフォリオ(再エネ+調整力+バックアップ等)をどう設計するかが、契約論を超えて運用設計のテーマになっています。
本シリーズでは「AIデータセンター時代のシステム設計」を、①ワット・ビット連携、②GX戦略地域、③PPA・電源ポートフォリオの実務論点――という3つの観点から、全3回で整理します。日本の最新の制度設計と接続して、実装するなら何が論点になるかに焦点を当てるのが狙いです。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年04月30日
分散型エネルギーとV2G(Vehicle to Grid)の可能性|Nuvve社 CEO来日特別対談 レポート
世界最先端のV2G(Vehicle to Grid)技術を有するNuvve社のCEO、Gregory Poilasne氏が来日し、東京で特別セッションが開催されました。本セッションでは、一般社団法人エネルギー情報センター理事であるRAUL株式会社の江田とGregory氏が対談を行い、日本のエネルギーシステムの未来とNUVVE JAPANの戦略について語られました。本記事では、当日のイベントの様子を時系列に沿ってご紹介します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年03月26日
系統用蓄電池のアグリゲーションについて|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ
2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、デジタルグリッド株式会社の豊田祐介氏が講演した「系統用蓄電池のアグリゲーション」について、その要約をご紹介します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年03月18日
系統用蓄電池での安全面や各種補助金について|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ
2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、電気予報士の伊藤 菜々 氏が講演した「系統用蓄電池での安全面や各種補助金」について、その要約をご紹介します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年03月18日
系統用蓄電池の導入事例について|系統用蓄電池ビジネス参入セミナーアーカイブ
2025年2月26日開催のオンラインセミナー「系統用蓄電池ビジネス参入セミナー」にて、株式会社パワーエックスの小嶋 祐輔 氏が講演した「系統用蓄電池の導入事例」について、その要約をご紹介します。