EVの終焉とエネルギー利権の戦い
発売日:2024年11月22日
出版社:ビジネス社

本書籍は、EVをめぐる現状と課題、そしてエネルギー利権の複雑な構造を鋭く分析した作品です。電動化技術の進展とともに、電気自動車業界が抱える矛盾や課題を指摘し、従来のエネルギー利権との対立や、政府や大企業の役割についても深く考察しており、日本のエネルギー戦略について新たな視点を与えてくれる一冊と言えます。
ITの専門家から見たEV事業の展望
本書籍は、電気自動車(EV)の未来に関する議論と、その背景にあるエネルギー市場の力学を掘り下げた一冊です。電動化技術の進展とともに、電気自動車業界が抱える矛盾や課題を指摘し、従来のエネルギー利権との対立や、政府や大企業の役割についても深く考察しています。
本書の特徴的な点は、単にEVの技術的な側面や市場動向を論じるだけでなく、世界的なエネルギー市場とその利権がいかにEVの普及に影響を与えているのかを明らかにしようとする点です。また、EVの終焉というタイトルが示唆する通り、著者はEVの普及には懐疑的な立場で議論を展開していきます。EVの普及に伴い予想外の新たな課題が浮上する可能性などを指摘しており、楽観的なEVの未来像に対して警鐘を鳴らしています。
特に興味深いのは、EVの普及を巡るエネルギー利権の戦いです。著者は、自動車業界、石油業界やガス業界のみならず国際間での政治的な利権・対立構造を解説し、加えて新しいエネルギー源への転換がどれほど経済的な圧力を生むかを説明しています。そのため、EVの発展が単なる技術革新にとどまらず、世界中のエネルギー政策や産業構造に深い影響を与えていることがよく理解できます。
ただし一方で、著者がITの専門家であるためだと考えられますが、一部エネルギー関連の記載には甘さが目立ちます。具体的には例えば、再生可能エネルギー発電促進賦課金については、固定価格で長期にわたり買取費用が積み立てられるため、制度の仕組み上として、回避可能費用が一定であれば原則として制度発足から20年程度は単価が上がっていく構造となっています。そのためFITの単価が段々下がっていっても、再エネ賦課金は上がっていくことになりますが、本書を読む限り制度の詳細等についてはリサーチが不足している部分もあるようです。
本書の後書きには、「こうやって転々と業態を変える弊社は、業界では「節操がない」とお叱りを頂いたり、「生命力がスゴイ」と感動されたり、賛否両論のなか、生き延びている。」との記載がありますが、まさに本書を現した表現だと感じます。オワコンや利権といった強い印象の言葉も少なからずありますが、非常に勢いがあり、情報が足りない部分は事業者等へのインタビューを行うなどして理論を補完し、その上で愛国心が溢れる形で文章をまとめ上げています。
全体としては、EVをめぐる現状と課題、そしてエネルギー利権の複雑な構造を鋭く分析した作品です。EVはグローバルなエネルギー利権の戦いとしての側面もあるという点を改めて捉え直すことで、日本のエネルギー戦略について新たな視点を与えてくれる一冊と言えるでしょう。
本ページの書評作成者
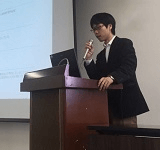
一般社団法人エネルギー情報センター
上智大学地球環境学研究科にて再エネ・電力について専攻、卒業後はRAUL株式会社に入社。エネルギーに係るITを中心としたコンサルティング業務に従事する。その後、エネルギー情報センター/主任研究員を兼任。情報発信のほか、エネルギー会社への事業サポート、また法人向けを中心としたエネルギー調達コスト削減・脱炭素化(RE100・CDP等)の支援業務を行う。新電力ネットの運営全般に係る統括責任者、また個人やご家庭の方への情報発信媒体として「電気プラン乗換.com」の立ち上げを行い、コンテンツ管理を兼務。
| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |
| 電話番号 | 03-6411-0859 |
| 社団HP | http://eic-jp.org/ |
| サービス・メディア等 | https://price-energy.com/ |







































