岐路にある再生可能エネルギー
発売日:2023年3月2日
出版社:エネルギーフォーラム
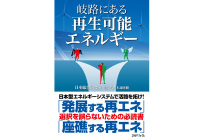
本書では、日本が取るべきエネルギー政策を「エネルギー政策の優先順位」、「再生可能エネルギーのリスク」、「日本独自の再生可能エネルギー政策」の三つの観点から述べています。
著者情報

日本総合研究所フェロー
日本総合研究所フェロー。1958年生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科修了後、三菱重工業に入社。1990年に日本総研へ。2021年に同社専務執行役員を退任し現職。アイフォー代表取締役、北陸産業活性化センター・エグゼクティブフェロー、NECエグゼクティブ コンサルタント、Team Energy顧問、DONKEY取締役会長も務める。
本書のコンセプトと構成/目次
日本型エネルギーシステムで活路を拓け!座礁する再エネと発展する再エネ、選択を誤らないための必読書- はじめに
- 第1章 ロシアのウクライナ侵攻で露呈したエネルギーリスク (1)世界を揺るがす化石燃料リスク
- 第2章 世界が目指すエネルギー自立 (1)エネルギー国産化
- 第3章 再生可能エネルギーを取り巻く3つのリスク (1)市場リスク
- 第4章 座礁する再生可能エネルギーと発展する再生可能エネルギー (1)座礁する大陸生まれの再生可能エネルギー
(2)先の見えない脱化石燃料のシナリオ
①水力発電―気候変動の影響が高まる水力発電
②風力発電―拡大する洋上風力
③太陽光発電―太陽光が主力とならざるを得ない日本
④バイオマス―BECCS期待のバイオマス
⑤資源調達期間が長い原子力発電―小型化というイノベーション
(2)エネルギー自立の本命、再生可能エネルギー
(2)気候変動リスク
①風力発電
②バイオマス発電
③太陽光発電
(3)ESGリスク
①再生可能エネルギーからのダイベストメント
②再生可能エネルギー全体に拡大
(2)ESG視点で再生可能エネルギーを再考する
(3)地域共生型再生可能エネルギー事業
著者インタビュー
ロシアによるウクライナ侵攻により、世界は改めてエネルギー政策の構造を根本から考え直さなくてはならなくなった。本書では、日本が取るべきエネルギー政策を三つの観点から述べている。
一つ目は、エネルギー政策の優先順位である。筆者を含め長くエネルギーに関わってきた者にとって、エネルギー政策の最優先課題はエネルギーセキュリティの確保である。しかし、近年、脱炭素を筆頭にエネルギーセキュリティ以外の要素が声高に叫ばれるようになった。脱炭素のほかにも、1980年代以来のエネルギー自由化、新自由主義の影を引きずったグローバル化などが、エネルギー産業の前提のように語られてきた。もちろん、おのおのについて根拠はある。脱炭素については、昨今の世界的な異常気象を見れば、焦眉の急とするのは当然だが、特定の電源に偏れば、エネルギーセキュリティは低下する。自由化やグローバル化については、ある時期は妥当な政策だったが、市場関係の政策の是非は経済環境によって変わる。近年では課題も見えてきており、立ち止まって再考すべきと考える人も少なくないはずだ。
二つ目は、再生可能エネルギーのリスクである。再生可能エネルギーの資源は国産の場合が多いから、その普及はエネルギーセキュリティの向上にも資する。しかし、われわれは、自然の恩恵に依存する再生可能エネルギーこそ自然環境の変動に最も大きな影響を受けるという当然の事態に直面しつつある。実際、出力の低下、台風による設備の損壊などの影響が顕在化している。それによりエネルギー供給が不安定になった事例もある。再生可能エネルギー普及の先にあるのは、決してバラ色のエネルギーシステムではないという認識が必要だ。
そして、三つ目は、日本独自の再生可能エネルギー政策である。メガソーラー、大型ソーラーファームは大陸で生まれた事業スキームだ。一方、広大な平地が広がる大陸国に比べ、日本では山地と平地が複雑に絡み合った国土に無数のコミュニティが偏在する。自然資源や生態系も繊細だ。そこで大陸生まれの大型再生可能エネルギー事業を一元的に普及すると、事業リスクが高まったり、コミュニティとのあつれきが生まれたりする。場合によっては、再生可能エネルギー事業が座礁資産化する事態にもなる。日本で再生可能エネルギーが普及するには、日本の自然環境やコミュニティと共生する独自の事業スキームが必要なのだ。
本書が、日本独自のエネルギー政策や再生可能エネルギー事業の普及にわずかながらでも貢献できることを期待したい。




































