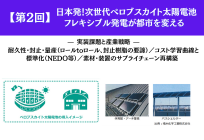風力発電の最新の国内動向や、課題と解決策について
| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |
一般社団法人エネルギー情報センター

三菱商事の洋上風力の入札案件や豊田通商の陸上風力開発など、風力発電関連のニュースが多く取り上げられています。再生可能エネルギーとして日本では太陽光に次ぐ導入ポテンシャルがある風力発電の最新の国内動向をご紹介。また、課題や解決のための取り組みについても取り上げます。
風力発電のポテンシャルとは
風力発電の現在の累積導入量は458万kw、2574基(2021年12月末時点)です。これは日本の発電エネルギー全体の中で1%程度です。ただ、その導入量は年々増えています。(以下図参照)

日本の風力発電導入量 出典:風力発電協会
カーボンニュートラル社会の実現を目指す2050年までに時間軸を伸ばすと、その導入ポテンシャルは高位シュミレーションで7000万kwにまでのぼります。

出典:環境省
陸上風力は安定的に風が吹くところや、自然環境や景観上問題が起こりにくい所などの適地限られますが、洋上風力は排他的経済水域世界第6位という海に囲まれた日本の立地を生かすことができ、大量導入が可能です。また、将来的なコスト低減による国民負担の低減効果や、地域社会の活性化や雇用の増加といった経済波及効果が大きいことから、「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札」と位置付けられています。
上記の図を見ると、中でも洋上風力の浮体式の導入ポテンシャルが高いことがわかります。日本の海域は遠浅が少ないこともあり、欧州で普及する着床式よりも浮体式の普及が期待されています。環境省によると、全国の洋上風力発電導入ポテンシャルの29%を九州エリアが占めており、次いで北海道エリア(26%)、東北エリア(14%)となっています。
政府は2020年12月に「洋上風力産業ビジョン」を取りまとめ、年間100万キロワット程度の区域指定を10年程度継続し、2030年までに1000万キロワット、2040年までに3000万~4500万キロワットまで拡大する導入目標を掲げています。
風力発電の直近の国内動向とは
企業の動向として、トヨタ通商や三菱商事の事例をご紹介します。また、政府の動向としては、日本版セントラル方式の検討が本格化しています。
トヨタ通商などによる国内最大級の陸上風力発電設備が2023年から稼働
北海道北部の稚内市から幌延町にまたがる地域で、トヨタ通商が5月に完全子会社化した国内風力最大手のユーラスエナジーホールディングスや、コスモエコパワー、Looopがそれぞれ発電を行います。2023年から稼働予定で、発電能力は54万キロワット。これにより北海道内の風力発電量は約2倍に増える見込みです。
また、国の補助金も活用し、送電網や蓄電池を合わせて開発することも特徴的です。大手電力事業以外ではまだ数が少ない事例となりますが、発電と送電を一体で整備し、再生可能エネルギー普及の課題である送電網の強化につなげるということです。将来的には北海道の風力で発電した電力を首都圏にも供給する方針です。
洋上風力3海域で三菱商事系が、売電価格「11.99円」で入札
2021年12月に、秋田県沖の海域と千葉県銚子市沖の海域で、洋上風力発電の公募を実施されました。国が発表した公募結果によると、三菱商事を中心とする事業体が3海域で全勝しました。その理由は、売電価格が1kw時あたり11.99~16.49 円であったことです。政府が設定した上限価格29円を大きく下回ったことで、メディアでも大きく注目されました。
当事業の本格導入は2028年~2030年を予定しています。政府は発電コスト(着床式)を2030~2035年までに8~9円/kWhにする方針です。また、風力発電が盛んな欧州では一般的な10円未満に迫る水準となっています。今回の入札によってそれらの水準に近づいてきたことになり、今までの参入ハードルを下げることになった事例といえるでしょう。
日本版セントラル方式の検討が本格化
セントラル方式とは、ヨーロッパでは主流となっている入札の仕組みです。国が一括して事前調査を実施した後に、事業者に入札をかけることで、複数の事業者による、風況や海底地盤等の洋上風力発電設備の基本設計に必要な調査項目のほか、環境影響評価で事業者が共通して行う項目についての重複実施が必要なくなるため、効率的にコスト削減をはかることができます。
そのため、導入目標に向けて案件形成を加速化していくことができます。政府は日本版セントラル方式の議論を進めていますが、費用負担の在り方についてなどの課題も残っています。
日本ならではの風力発電の課題とは
風が吹くことで発電することが特徴ですが、一方で台風のような強すぎる風であると、発電施設が破損する恐れがあります。そのため台風が多い日本で故障のリスク高いと言われています。
風力発電機には10,000点以上の部品が使われており、メンテナンスが大切です。ただ、部品の多くを輸入に頼っている現状です。そのため、故障が起きると設備を止める必要があり、その間の設備利用率が低下します。安定した発電を行うためには日々の点検で故障のリスクを最少にする必要があります。このように、保守や維持運営にコストがかかり、さらにはそうした管理やメンテナンスをする人材が不足しているという現状があります。同時に海外製の発電機や部品が多いので、サプライチェーンの問題もあります。
また、洋上風力は陸上に比べて機械を大型化できるというメリットがある一方で、その製造や設備にかかるコストが高いという点があります。
風力発電の直近の国内動向とは
そこで、このような課題を解決するために自治体や企業によって産業の創造の動きや新しい機会が開発させています。今回は、北九州市とアルバトロス・テクノロジー社についてご紹介します。
洋上風力関連の総合拠点を目指す北九州市の取り組み
北九州市では、部品製造の内製化からメンテナンスまで、洋上風力関連の総合拠点を目指しています。新しい産業として根付かせるために研究・開発や人材育成ができる企業などを積極的に誘致するの取り組みを行っています。
北九州市は、平成28年8月より北九州港内の水域(約2,700ha)を対象に、洋上風力発電事業者の公募を開始しました。同市は、響灘地区の広大な産業用地や充実した港湾施設などのポテンシャルを活かし、産業の裾野が広く雇用創出効果が高い風力発電をターゲットに据え、あらゆる機能が集積した「風力発電関連産業の総合拠点」の形成などを目指した「グリーンエネルギーポートひびき」事業を22年度より推進しています。総事業費は約1,750億円、5メガワット級の洋上風力発電施設を最大44基設置し、34年度より着工し、順次運転が開始される予定です。

総合拠点イメージ 出典:北九州市
風車はナセル、タワー、ブレード及び基礎といった重厚長大な部材で構成されており、その荷揚げ、運搬・保管、事前組立や洋上への積出しを安全で効率よく行うには、高い耐荷重性を備えた荷さばき地と岸壁が不可欠となります。これらを備えたものが「基地港湾」です。現在、本市では、総合拠点の基盤となるインフラで、主に「風車積出拠点」機能に必要不可欠な「基地港湾」の整備を進めており、令和2年度からはその一部を国の事業として国が整備することになりました。基地港湾が響灘洋上ウインドファーム事業で利用されることにより、洋上風力発電に関わる新しい産業が基地港湾及びその周辺に創出されることが期待されています。
垂直軸型風車開発のアルバトロス・テクノロジー、2040年に実証実験
アルバトロス・テクノロジーは2012年創業のベンチャー企業です。浮体式の垂直軸型風車(Floating Axis Wind Turbine:FAWT)の開発に取り組んでいます。2022年9月14日、総額1億円の資金調達を行い、小型海上実験の準備を開始したと発表しました。
アルバトロス・テクノロジーは2012年創業のベンチャー企業です。浮体式の垂直軸型風車(Floating Axis Wind Turbine:FAWT)の開発に取り組んでいます。2022年9月14日、総額1億円の資金調達を行い、小型海上実験の準備を開始したと発表しました。

出典:アルバトロス・テクノロジー
傾斜しても回転性能が低下しにくく、最大出力時に20度までの傾きを許容できるといいます。こうした特徴から、強風時などに垂直不動を維持するための大型浮体が不要です。また、クレーンを使わずに組立・海上設置が可能なため、水深の浅い港も基地港にできます。結果、製造・設置・保守といった総合的なコストの低減を図ることができるということです。
さらに、発電機も含めて100%国内調達が可能なデザインだといいます。先述したサプライチェーンの問題やメンテナンスの人材不足の課題解決にもつながります。風車産業の国産化による国内経済への還元にもつなげていきたいということです。
今後の展開として同社では、2024年度に小型機の海上実験を開始する予定としており、今後の大型機の海上実証プロジェクトに繋げていきます。大型機で実証済みとなれば、商用機のプロバイダーとして風力発電事業社らと提携し、国内外の洋上風力入札に参加できるようになるということです。
Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター
EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。
| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |
|---|---|
| 所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |
| 電話番号 | 03-6411-0859 |
| 会社HP | http://eic-jp.org/ |
| サービス・メディア等 |
https://www.facebook.com/eicjp
https://twitter.com/EICNET |
関連する記事はこちら
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年10月29日
前編では、ペロブスカイト太陽電池の特性と政策的背景、そして中国・欧州を中心とした世界動向を整理しました。 中編となる今回は、社会実装の要となる耐久性・封止・量産プロセスを中心に、産業戦略の現在地を掘り下げます。ペロブスカイト太陽電池が“都市インフラとしての電源”へ進化するために、どのような技術と制度基盤が求められているのかを整理します。特に日本が得意とする材料科学と製造装置技術の融合が、世界的な量産競争の中でどのように差別化を生み出しているのかを探ります。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年10月27日
中小企業が入れるRE100/CDP/SBTの互換ともいえるエコアクション21、GHGプロトコルに準じた「アドバンスト」を策定
GHGプロトコルに準じた「エコアクション21アドバンスト」が2026年度から開始される見込みです。アドバンストを利用する企業は電力会社の排出係数も加味して環境経営を推進しやすくなるほか、各電力会社側にとっても、環境配慮の経営やプランのマーケティングの幅が広がることが期待されます。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年10月18日
日本発!次世代ペロブスカイト太陽電池:フレキシブル発電が都市を変える 【第1回】背景と技術概要 — 何が新しいか/政策・投資の全体像/海外動向との比較
本記事は、2024年公開の「ペロブスカイト太陽電池の特徴とメリット」「ペロブスカイト太陽電池の課題解決と今後の展望」に続く新シリーズです。 耐久性や鉛処理、効率安定化といった技術課題を克服し、いよいよ実装段階に入ったペロブスカイト太陽電池。その社会的インパクトと都市エネルギーへの応用を、全3回にわたって取り上げます。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年10月17日
非化石証書(再エネ価値等)の下限/上限価格が引き上げ方向、脱炭素経営・RE100加盟の費用対効果は単価確定後に検証可能となる見込み
9月30日の国の委員会で、非化石証書の下限/上限価格の引き上げについて検討が行われています。脱炭素経営の推進を今後検討している企業等は、引き上げ額が確定した後にコスト検証を実施することが推奨されます。また本記事では、非化石証書の価格形成について内容を見ていきます。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年09月29日
【第3回】電力小売に導入が検討される「中長期調達義務」とは ——料金・市場構造・投資への影響と導入後の論点—
第1回では制度導入の背景を整理し、第2回では設計の仕組みと現場課題を取り上げました。最終回となる本稿では、中長期調達義務が導入された場合に、料金や市場構造、投資意欲にどのような影響が及ぶのかを展望します。
制度の目的は電力の安定供給を強化し、価格急騰のリスクを抑えることにあります。ただし、調達コストの前倒し負担や市場流動性の低下といった副作用も想定されます。今後は、容量市場や需給調整市場との整合性、データ連携による透明性、新規参入環境の整備といった論点への対応が、制度の実効性を左右することになります。