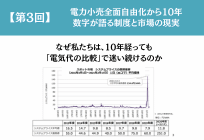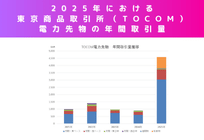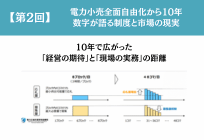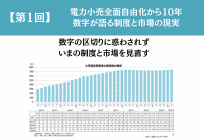お得感を引き出すマーケティング②~電気料金プランのポイント割引は有効?~
| 政策/動向 | 再エネ | IT | モビリティ | 技術/サービス | 金融 |
スカイライトコンサルティング株式会社

前回は「お得感を引き出すマーケティング」としてまずセット販売の有効性についてお話ししました。今回はその続きとして「疑問3:ポイント割引は有効?」という疑問に対して、ポイントプログラムの活用による「お得感の引き出し方」のお話をさせて頂きます。
イントロダクション
前回は「お得感を引き出すマーケティング」としてまずセット販売の有効性についてお話ししました。今回はその続きとして「疑問3:ポイント割引は有効?」への答えとして、ポイントプログラムの活用による「お得感の引き出し方」のお話をさせて頂きます。
まず、理解していただきたいのは、ポイントプログラムを導入したからといって、それだけで消費者に訴求することはできないことです。業界問わずあまたのポイントプログラムが既に存在し、流通・小売業界を中心に顧客獲得・維持のために火花を散らしている中、「電力ポイント」をつけたからといって、大きなマーケティング効果は望めません。それにもかかわらず、むやみに自社の独自ポイントを推進してしまうと、利益を失うだけになってしまいます。ポイントプログラムは結局は自社利益の還元であり、ポイント提供による販売増が見込めなければ、事業収益にプラスの効果は出ないからです。
では、マーケティングの話に行く前に、そもそものポイントプログラムの特性について解説しましょう。
人々は何故ポイントを集めるのか?
消費者は何故ポイントを貯めるのでしょうか?それは、商品やサービスの購入・利用時に付与されるポイントには、ある一定の条件下(ポイントの利用条件や利用できる場所・タイミングなど)において現金(通貨)と同様の機能、つまり、一種の「疑似通貨」としての価値があるからです。
疑似通貨としてポイントがもつ機能
- 価値尺度機能:モノやサービスの価値を相対的に示すことができる(○○ポイントで××と交換可能)
- 価値保存機能:ポイントを貯めてその価値を保存できる(現在のポイントは△△ポイントです)
- 交換機能:モノやサービスの交換の手段となる(本ポイントの利用可能店舗・サービス一覧)
これらは現金と同じ機能であり、ポイントにおいてもこれらが消費者にとってのポイントを集める基本的な動機と言えます。
ポイントプログラムの成功事例
ポイントプログラムの先駆けであり、成功事例として紹介されることが多いのは航空会社のマイレージプログラムです。その他にも家電量販店のポイント還元制度や大手ECサイトの利用ポイントなど、様々な業界・企業においてポイントプログラムが取り入れられています。また近年では、一企業が独自に運営するものだけでなく多数の企業が相乗りで利用することを前提に運営されている「共通ポイント」の利用も拡大しています。以下にポイントプログラムの一般的な種類を示します。
ポイントプログラムの種類
独自ポイント
自社独自でポイント付与・交換を運営する形態。利用は自社が取り扱う商品・サービスでの利用に限定されるが、運営の自由度は高い。
提携ポイント
独自ポイント同士が一定条件のもとで提携し、相互利用できる形態。利用範囲が提携先の商品・サービスまで広がるが、運営の自由度は低下する。
共通ポイント
複数の企業が利用することを想定した統一ブランドでのサービス形態。導入負担は少なくポイントの利用範囲も広いが、運営の自由度はほとんどない。
実際、みなさんも多くのポイントプログラムを利用していると思います。その中でも良く使うものとそうでないものがあるのではないでしょうか。その違いは何なのでしょうか?
ポイントの価値を高めるには前述した疑似通貨としての3つの機能のいずれか(もしくは全部)において他のポイントプログラムにはない魅力を消費者に訴求することが重要です。特に魅力的な交換内容の提示(価値尺度機能の訴求)とポイント経済圏の拡大(交換機能の訴求)がポイントプログラムにおける基本的な戦略となります。(※価値保存機能については、現金と違ってポイントには期間限定のものもありますが、その長期にわたって有効なものがほとんどであり、単体では大きな差別化にはなりにくい。)
魅力的な交換内容の提示
次にポイントプログラムを活用する際の差別化ポイントについて考えます。ひとつめの魅力的な交換内容の提示(価値尺度機能の訴求)するのはどうしたら良いでしょうか?そのためにはまず消費者が何に魅力的と感じるかを知る必要があります。ポイントを貯める際に生じやすい行動特性としてよく知られているものに行動経済学における「保有効果」と「選考の逆転」があります。
ポイントを貯める際の一般的な消費者の行動特性
保有効果
自分が所有するものに高い価値を感じ、手放すことに抵抗を感じさせる。
→適用例:たくさんポイントを貯めたほうが、より良い(高額な)モノ・サービスが手に入る
選考の逆転
人の思考や好みがその場の状況や文脈・印象によって左右される。
→10%現金値引きと、10%ポイント付与では、現金値引きの方が本来お得のはずだが、貯めて使えるという価値の方が勝る場合がある
つまり2つの特性をうまく組み合わせて「ポイントを貯めること」自体に価値を感じるようにさせることが、結果的に「魅力的な交換内容を提示」することに結びつく訳です。
ポイント経済圏の拡大
もう一つの差別化要素としてポイント経済圏の広さ(交換機能の訴求)はどうでしょう。経済圏の広さの訴求が近年のトレンドなっている例として、リクルートやソフトバンクなどが独自のポイントプログラムから共通ポイントプログラムへ乗り換えるなど「ポイントが貯まりやすい」から「貯まったポイントが使いやすい」への変化がここ数年で加速しています。
たとえばソフトバンクでは2014年にこれまでの独自ポイントを共通ポイントに切り替えたところ、顧客満足度が3割程度アップしたとのことです。これは自社の経済圏だけで利用できるポイントで囲い込むよりも、より大きいポイント経済圏(交換しやすい)のプログラムに変更することで、顧客への価値訴求が高まるということを示す実例と言えるでしょう。
個人向け電力市場における現状の取り組み
では個人向け電力市場においてはどうでしょう?
電気利用額に応じたポイントプログラムを導入することは、電気料金の実質的な値引きを利用者に提示できるという価値があります。特に制度的な制約があり電気料金に関して他社に大きな差がつけることが難しい既存電力会社ではポイントプログラムの導入はとても魅力的な価値訴求方法と言えます。実際に小売電力自由化前から多くの既存電力会社が独自にポイントプログラムを導入していました。一方で4月以降は共通ポイントプログラムとの提携が次々と行われています。
- 電気料金の値下げが難しい既存電力会社や顧客基盤が大きいガス会社などでは、お得感の訴求手段としてポイントプログラムの導入に積極的
- 小売電力自由化に伴い特に単なる値引きの代替手段ではなく「経済圏」の広さを意識した共通ポイントプログラムとの提携が次々と行われている
電力会社と共通ポイントプログラムとの提携例
| ポイントプログラム名 | 提携電力会社 |
|---|---|
| Tポイント | 東京電力、中部電力、ソフトバンクでんき、ENEOSでんき、東京ガス、西部ガスなど |
| Ponta | 東京電力、関西電力、東北電力、まちエネ、東京ガス、西部ガスなど |
市場特性を考慮した有効活用に関する提言
ここまでお話したポイントプログラムの特性を踏まえ、個人向け電力市場において他社と差別化を図るにはどうしたら良いでしょうか。例えば東北電力が4月から開始したか個人向け会員サイト「よりそうeねっと」では、「よりそうeポイント」という独自のポイントプログラムを展開しており「地域とのつながり・地域貢献」を訴求するとともに、共通ポイントと交換可能という形での経済圏の拡大にも力を入れています。
交換価値の訴求
- ポイントを東北6県と新潟県のご当地商品に交換できる
- たまったポイントを、震災復興支援や、地域の雇用創出・人材育成などを行なっている基金に寄付
経済圏の拡大
- コンビニなどで使える電子マネー・共通ポイントに交換できる
- 商品券・ギフト券へ交換できる
「よりそうeねっと」は開始から3か月で獲得会員が10万人を突破しており、ポイントプログラムの有効活用事例として新電力系の企業も参考にすべき点があると思います。異業種という点では、例えば大手石油卸売会社系列のサービスステーションではガソリン以外商品・サービスの購入利用に応じてガソリン代金を値引く方策が長くとられており、電力利用についても同種の割引を適用する会社が出てきています。
また市場特性を考慮するという視点では、ポイントプログラムのトレンドとして意図的に“ためる”から無意識に“たまる”(つまり、特別な意思表示がなくとも消費するだけで自動的にポイントが付与される)仕組みへシフトしつつある点にも注目すべきです。
一定量の消費が継続的かつ長期間にわたり行われる電力消費の特性はポイントプログラムの上記トレンドとマッチしており、この特性を盛り込んだ工夫をすることによりポイントプログラムの利用者を大幅に増やせる可能性もあります。
電気消費の特性とポイントプログラムの親和性
- ポイント獲得を意識せずに行う(手間をかけずにたまる、手に入る)
- ポイント獲得となる消費を継続的に行う(継続的に一定量の消費が見込める)
小売電力自由化への対応として、電力会社とポイントプログラムの運営企業との連携が盛んに行われている背景には、こうした消費特性と顧客数の大きさに目を付けたポイントプログラムの運営側からのラブコールも多分にあるという訳です。
今回のまとめ
「お得感を引き出すマーケティング②」として今回はポイントプログラムについて取り上げ、その有効活用について考察しました。プログラムの差別化には、魅力的な交換内容の提示(価値尺度機能の訴求)とポイント経済圏の拡大(交換機能の訴求)が重要である点がまずはご理解いただけたでしょうか。
ポイント
- 個人向け電力市場でもポイントプログラムの活用が急速に広まっている
- 魅力的な交換内容の提示(価値尺度機能の訴求)とポイント経済圏の拡大(交換機能の訴求)が差別化のカギ
- 価値尺度機能の訴求では行動経済学における「保有効果」と「選考の逆転」を考慮する
- 交換機能の訴求には共通ポイントとの連携などによる経済圏の拡大が有効
- 市場特性を活かした無意識に“たまる”仕組みの導入も効果的
この続きを読むには会員登録(無料)が必要です。
無料会員になると閲覧することができる情報はこちらです
前の記事:お得感を引き出すマーケティング①~電力のセット販売は有効?~
Facebookいいね twitterでツイート はてなブックマーク執筆者情報

一般社団法人エネルギー情報センター
EICは、①エネルギーに関する正しい情報を客観的にわかりやすく広くつたえること②ICTとエネルギーを融合させた新たなビジネスを創造すること、に関わる活動を通じて、安定したエネルギーの供給の一助になることを目的として設立された新電力ネットの運営団体。
| 企業・団体名 | 一般社団法人エネルギー情報センター |
|---|---|
| 所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目9−22 多摩川新宿ビル3F |
| 電話番号 | 03-6411-0859 |
| 会社HP | http://eic-jp.org/ |
| サービス・メディア等 |
https://www.facebook.com/eicjp
https://twitter.com/EICNET |
関連する記事はこちら
一般社団法人エネルギー情報センター
2026年02月11日
電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第3回】なぜ私たちは、10年経っても「電気代の比較」で迷い続けるのか
電力小売全面自由化から10年が経過し、電気料金のメニューや契約形態は大きく多様化しました。 一方で、どの電気契約が有利なのかという問いは、いまも多くの現場で解消されないまま残っています。 見積書を並べ、単価を比較し、条件を読み込んでも、最後の判断に踏み切れない。こうした迷いは、単なる理解不足や情報不足として片づけにくいものになっています。 判断が難しくなる背景には、情報の量ではなく、比較に持ち込まれる情報の性質が揃わなくなったことがあります。 単価のように「点」で示せる情報と、価格変動や運用負荷のように時間軸を含む「線」の情報が、同じ比較枠の中で扱われやすくなっているためです。 本稿では、この混線がどこで起きているのかを整理します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2026年01月19日
2025年の電力先物市場:年間取引量4,583GWhで過去最高更新、年度物導入と中部エリア上場を控えた市場の変化
価格変動リスクへの対応を意識した取引行動が、実務レベルで具体化し始めた一年となりました。 制度面では年度物取引の導入、取引環境では流動性改善やコスト低減策が進み、企業側では中長期のヘッジ設計を見直す動きが重なりました。こうした複数の要因が同時に作用した結果、東京商品取引所(TOCOM)における電力先物の年間取引量は約4,583GWhと、前年比約5倍に拡大し、過去最高を更新しています。 中でも、東エリア・ベースロード電力先物が前年比約5倍、西エリア・ベースロード電力先物が前年比約3倍と伸長し、主要商品の取引が全体を押し上げた形となりました。加えて、2025年5月に取引を開始した年度物取引も、市場拡大を牽引する要素となっています。 本稿では、2025年通年の動向を中心に、市場拡大の背景と今後の論点を整理します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2026年01月19日
電力小売全面自由化から10年 数字が語る制度と市場の現実【第2回】10年で広がった、「経営の期待」と「現場の実務」の距離
「自由化から10年」という節目を迎え、制度の成果や市場の成熟度をめぐる議論が活発化しています。 現場の会話をたどると、同じキーワードでも立場により意味がずれます。 たとえば、経営の「コスト削減」は現場では「業務負荷の増加」、制度側の「安定供給」は供給現場では「柔軟性の制約」として現れます。 第2回では、こうした変化のなかで生じている立場ごとの認識のずれを整理し、経営・現場・供給事業者という三つの視点から、なぜ議論が噛み合わないのかを構造的に考察します。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年12月31日
電力小売全面自由化から10年、数字が語る制度と市場の現実【第1回】数字の区切りに惑わされず、いまの制度と市場を見直す
「自由化から10年」という言葉が、各所で頻繁に取り上げられるようになりました。 しかし、制度の導入や市場設計の見直しが今も続いており、電力を取り巻く環境は「完成」に近づくどころか、なお変化の途上にあります。 本稿では、数字がもたらす完了感と、制度・市場の実態との間にあるずれを整理し、“節目”という言葉の意味をあらためて考えます。
一般社団法人エネルギー情報センター
2025年12月27日
政府も注目する次世代エネルギー 核融合の仕組みと可能性 【第5回】社会実装と中長期シナリオ 2030年代のロードマップと日本の戦略
これまで4回にわたり、核融合という次世代エネルギーの可能性を、研究・技術・制度の観点からたどってきました。長らく“夢のエネルギー”と呼ばれてきた核融合は、いま確実に社会の現実へと歩みを進めています。 最終回となる今回は、社会実装に向けたロードマップと、日本が描くべき中長期戦略を考えます。 核融合が“希望の象徴”で終わらず、私たちの暮らしに息づくエネルギーとなるために、次の時代に向けた道筋を描きます。