VUCA時代のエネルギー戦略
発売日:2024年1月28日
出版社:エネルギーフォーラム
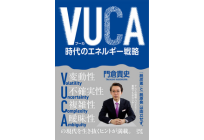
「脱炭素」と「脱原発」は両立せず――「Volatility(変動性)」、「Uncertainty(不確実性)」、「Complexity(複雑性)」、「Ambiguity(曖昧性)」の現代を生き抜くヒントが満載。
著者情報

エコノミスト・BRICs経済研究所代表
1971年神奈川県生まれ。1995年慶応義塾大学経済学部卒業、同年銀行系シンクタンク入社。1999年日本経済研究センター出向、2000年シンガポールの東南アジア研究所出向。2002年から2005年まで生保系シンクタンク経済調査部主任エコノミストを経て現職。同研究所の活動のほか、フジテレビ『ホンマでっか!? TV』、読売テレビ『クギズケ!』、テレビ朝日『ビートたけしのTVタックル』など各種メディアにも出演中。また、雑誌・WEBでの連載や各種の講演も精力的に行っている。さらに、『図説BRICs経済』(日本経済新聞出版)、『増税なしで財政再建するたった一つの方法』(角川書店)、『日本の「地下経済」最新白書』(SB新書)など著書も多数。
解説
現代は、変化が激しく先行き何が起こるかわからないVUCA(ブーカ)の時代である。ここ1~2年でも、ロシアのウクライナへの軍事侵攻やイスラエルとイスラム過激派組織ハマスの軍事衝突など、VUCAと呼ぶべき事象が国際社会で頻繁に発生するようになっている。 筆者は仕事柄、個人投資家向けの講演をすることが多いが、VUCAの時代には、リスクを小さくするという観点から、これまで以上に分散投資の重要性が高まることを普段から指摘している。このような資産運用における分散投資の考え方は、そのままエネルギー戦略にも適用できる。 エネルギー資源は、石炭・石油・天然ガスといった化石燃料、太陽光・風力・バイオマス(生物資源)・地熱といった再生可能エネルギー、そして原子力の3つに大別される。これまでの日本のエネルギー政策は、化石燃料に極端に頼っていたが、化石燃料に依存したエネルギー政策は環境への適応の観点でリスクが大きい。実際、1990年代後半以降、国際社会では、地球温暖化対策として脱炭素化が呼びかけられてきた。2023年にアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催された国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)においても、産業革命前からの気温上昇を1・5℃以内に抑えるため脱炭素化を加速させることが宣言された。また米国政府も、原子力エネルギーが重要な役割を果たすとし、2050年までに世界の原子力発電所の発電容量を3倍にすることを目指すと宣言、日本を含む20カ国以上が賛同している。 今回、世界主要国のエネルギー政策を詳細に分析したところ、脱炭素化を実現するためのエネルギー政策の方向性は2つのパターンに分けることができた。1つ目のパターンは、安全性の観点から原発という選択肢を排除したうえで、再生可能エネルギーだけで将来のカーボンニュートラルを実現していくというものだ。2つ目のパターンは、技術的に可能なあらゆる選択肢を排除することなく、化石燃料の代替エネルギーとして再生可能エネルギーと原子力を組み合わせて、将来のカーボンニュートラルを実現しようというものだ。 各国のエネルギー政策のこれまでの経過をみれば、「脱炭素」と「脱原発」の二兎を追うことが不可能なのは明白だ。脱原発を決めたドイツでは、再生可能エネルギーの導入を加速させたが、それによって一般家庭や企業の電気料金が高騰するようになり、今度は電気料金を抑えるために、安価な石炭火力発電を使うという脱炭素化に逆行するような動きが出てきている。 脱炭素、エネルギーコストの抑制、エネルギー安全保障の強化を同時に実現するには、再生可能エネルギーと安全性が確認された原子力発電の組み合わせがベストな方策になるのではないか。
本書の内容
- はじめに――VUCAとは何か? 現代は予測不可能の時代 VUCAの時代には不測の事態に備えてエネルギー自給率を高めることが重要
- 第1章 コロナ禍とエネルギー価格 コロナショックで世界経済が未曾有の危機に直面 日本の自動車メーカーの世界戦略にもマイナスの影響 2020年は世界大恐慌以来のマイナス成長 コロナショックで原油価格が史上初のマイナスに ロシアとサウジアラビアの価格競争が原油価格の下落に拍車をかけることに ワクチンの開発・普及状況と連動する原油価格 上海市のロックダウンの影響で乱高下した原油価格 コロナショックでLNGプラント建設が抑制される!? コロナショックで米国シェール企業の破たんが相次ぐ事態に 太陽光や風力発電市場にも影響 新型コロナウイルスはバイオマス発電にも影響
- 第2章 ロシアの軍事進攻とエネルギー価格 2022年2月に始まったプーチンの戦争 ロシアの資源輸出を止められなかった「金融の核爆弾」 ロシアが欧州への天然ガス供給を制限 欧州の爆買いでLNG価格が高騰 戦略備蓄放出の効果は? 欧米の禁輸措置で原油価格が高騰 ロシア産の石炭の禁輸でセメント価格が高騰 欧州各国で復活した石炭火力発電 ロシアのウクライナへの軍事侵攻で木質バイオマス発電の採算が一段と悪化
- 第3章 エネルギー価格の高騰と家計・企業負担の増大 コストプッシュインフレに直面する日本経済 家計の光熱費負担が増大 脱炭素社会への移行を遅らせる政府の補助金政策 エネルギー価格の高騰で中小企業の収益環境が悪化 テーマパークや遊園地、水族館にも値上げの波 中東情勢の不安定化でガソリン価格にさらなる上昇圧力も
- 第4章 諸外国のエネルギー戦略 トランプ政権とバイデン政権で180度変わった米国のエネルギー政策 原子力発電の拡大を急ぐ英国 「原子力ルネサンス」を宣言したフランス 再生可能エネルギーと原子力発電の導入を進めるカナダ 原発推進に舵を切ったオランダ 洋上風力発電に注力するドイツ 再生可能エネルギーだけで脱炭素化を目指すイタリアとオーストリア 脱炭素・脱原発で2050年のカーボンニュートラル実現を目指すスイス 再生可能エネルギーだけでカーボンニュートラルの実現を目指すデンマーク 原子力発電所を活用して脱炭素化を目指すスウェーデン 政権交代で脱炭素化に舵を切った豪州 原子力発電推進に回帰する韓国 中国は2060年のカーボンニュートラル実現を目指す 原子力大国を目指す中国 日本の原発処理水の海洋放出を政治問題化する中国 大気汚染の問題解決のために脱炭素化を目指すインド 地熱発電の開発・導入に注力するインドネシア 脱水力発電を目指す南米のブラジル グリーン水素の生産・輸出大国を目指す南アフリカ共和国 原子力発電所の導入を急ぐトルコ 米国企業がポーランドの原子力発電所を受注 ウクライナ侵攻以降、原子力発電所の輸出に力を入れるロシア
- 第5章 エネルギー政策にも分散投資の考え方を 人生100年時代のリスクとは? ゆとりのある老後の生活をするのに理想の資産額は1億円? リスク分散の効果が大きいオルタナティブ投資 北海道の「ブラックアウト」は一極集中型のエネルギーシステムが原因? 日本のエネルギー政策にも当てはまる分散投資の考え方 再生可能エネルギーにもリスクがある
- 第6章 日本のグリーントランスフォーメーション(GX)戦略 2050年までに脱炭素社会の実現を目指す 次世代のクリーンエネルギーとして注目される水素 ガスのカーボンニュートラルを実現する「メタネーション」 次世代のクリーンエネルギーとして注目されるアンモニア CO2を回収して地下に貯留するCCSの技術 安全性の高い次世代革新炉 EV普及のカギを握る販売価格の引き下げ 個別企業もGX推進でメリットを享受
- おわりに
- 参考文献
- 著者紹介







































